CAMRは状況変化の技法?(その7 最終回)
Aさんはその3週間後に、自分の脚と杖で歩いて退所されました。まだ膝が痛むことはあるものの、痛みなく歩けるコツが少しずつ分かってきたそうです。
さらにAさんはご家族がいくら言っても聞いてもらえなかった紙パンツと尿パッドを付けての退所でした。
もちろん根本の原因である頻尿・失禁の問題は解決していませんが、元々それが私達の仕事ではありません。ご家族の要望通りに「失禁が大変負担」という問題を解決することが目標でした。
以前は尿失禁のために、毎日たくさんの洗濯物や毎回のトイレ掃除だけでたくさんの労力と時間を費やしていたそうですが、これ以降は全く問題がなくなったそうです。
ご本人さんは問題解決に向けて、皆にアドバイスを求めて、結局、骨盤底筋や腹横筋の筋力強化もやられるようになりました。「単に尿を止めるために締めるだけでなく、尿をたくさん出し切ることも大事だろう」とAさん自身が計画を立てられたので、それに応えてトレーニングを計画しました。
もともと機械の設計をしておられただけに論理的で現実的です。もちろんすぐに効果は見られていません。退院後に、ご家族が希望されていた泌尿器科の受診もされるとご本人が決められました。
どうも後から分かったことですが、Aさんは元々普段から妻が一方的に受診だの、歩けだの、施設でトレーニングだのとうるさく繰り返すので、それに対する反発がこじれてしまったようです。僕に対しても「妻は一旦言い始めると制御ができなくて、言い続けるから嫌になるんだ。だから妻の言う通りには絶対になるまいと意地を張っていた」と笑われていました(^^;))僕もそこは素直に共感しました・・・なんてウソです、僕は妻にはそんなこと思ってませんからね(^^;)
今回は、ユニットでの介護問題の解決がリハビリでの訓練拒否問題の解決にも繋がりました。Aさんとの経験で、僕たちのリハビリドック・チームは自信を付けたと思います。いつも「起こせる状況変化を起こし、良ければ繰り返し、ダメなら他の状況変化を!」と考えます。
特に状況変化のやり方は無限に存在すると言っても良いのですが、今回のようにコミュニケーションのやり方を変化させる、コミュニケーションの立場を変化させることはとても有効であると気づかされました。これ以降は状況変化の第一選択に、コミュニケーション関係の変化を持ってくるようになりました。
今回のエッセイは、2017年発行の拙書「PT・OTが現場ですぐに使えるリハビリのコミュ力」西尾幸敏(金原出版)で掲載しなかったエピソードの一つに加筆・修正したものです。本書には老健のリハビリドック・チームの取り組みがいくつか紹介されています。
たとえば徘徊の認知症老人と職員のコミュニケーションを変化させることで徘徊の問題が解決した例や支配的な夫の一方的な介護関係で苦しんでおられた妻にとっての「言葉のやりとり」から「身体のやりとり」というコミュニケーションに変化させることで問題解決が行われた例、その他などが載っています。
興味のある方は是非ご一読くださいv(^^)
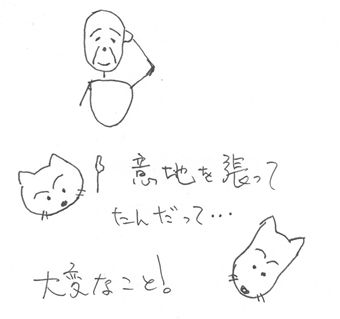


カテゴリ:CAMRは状況変化の技法 [コメント:0]














コメントフォーム