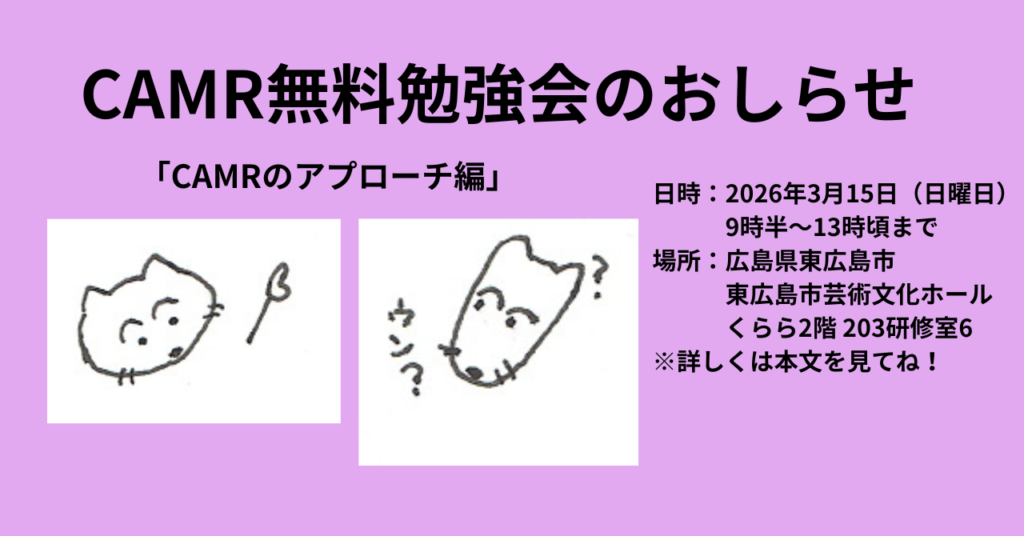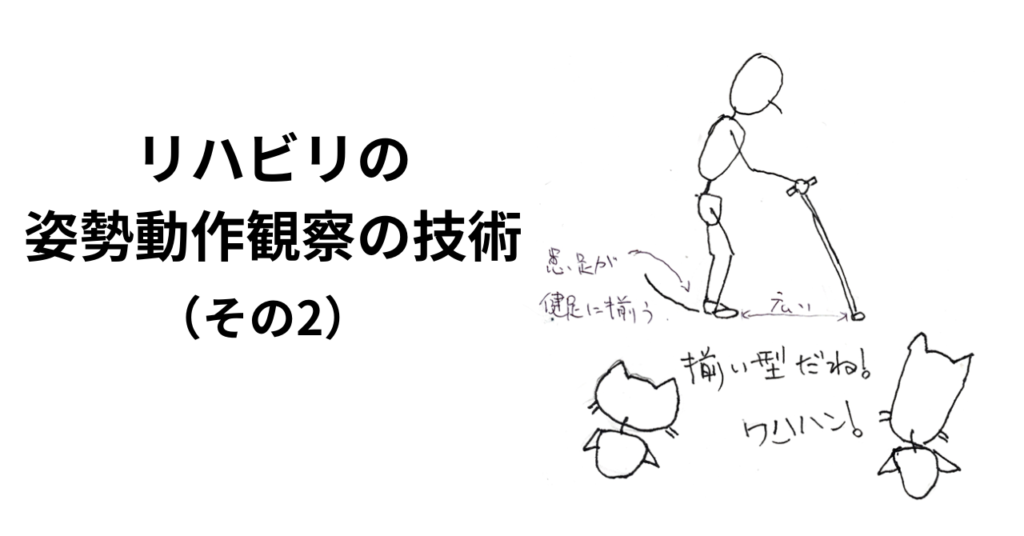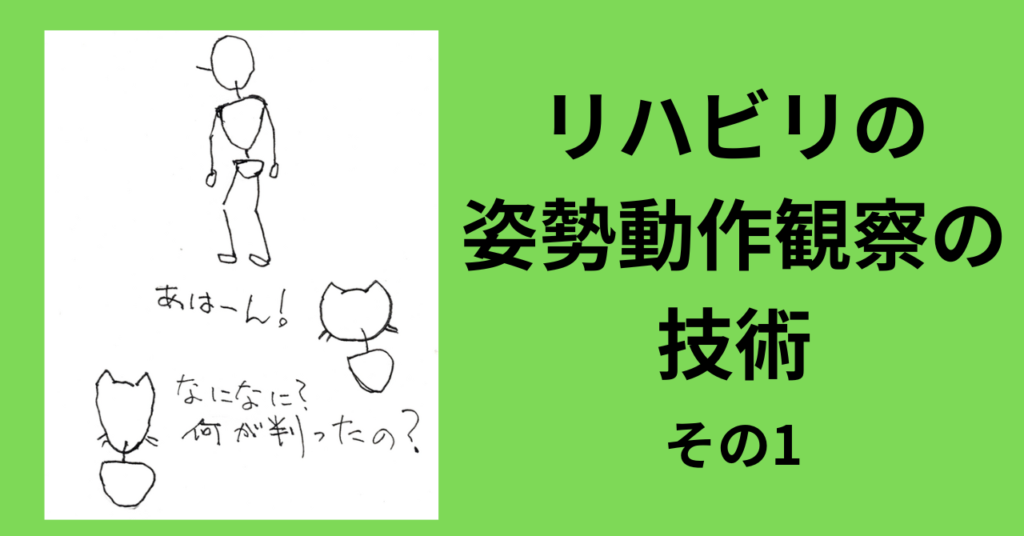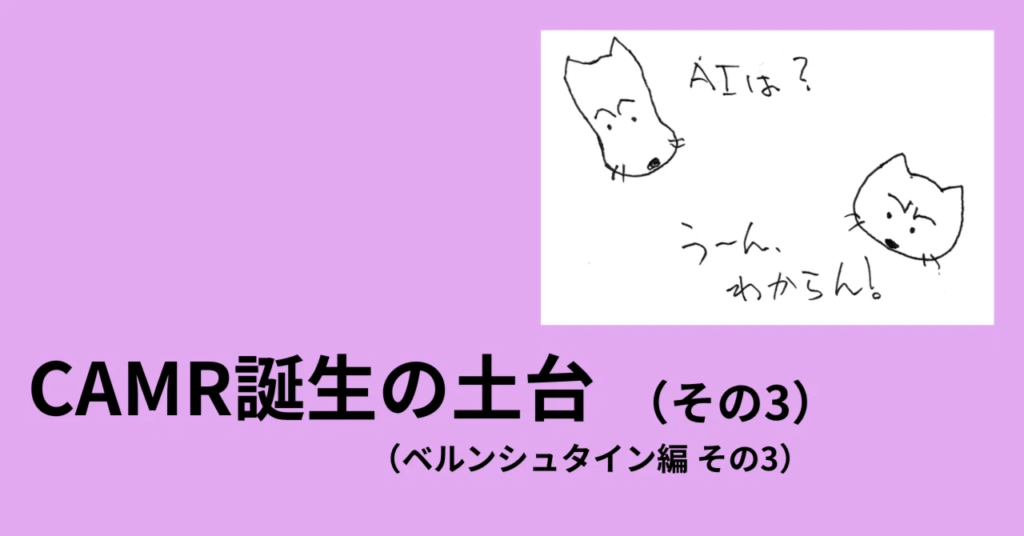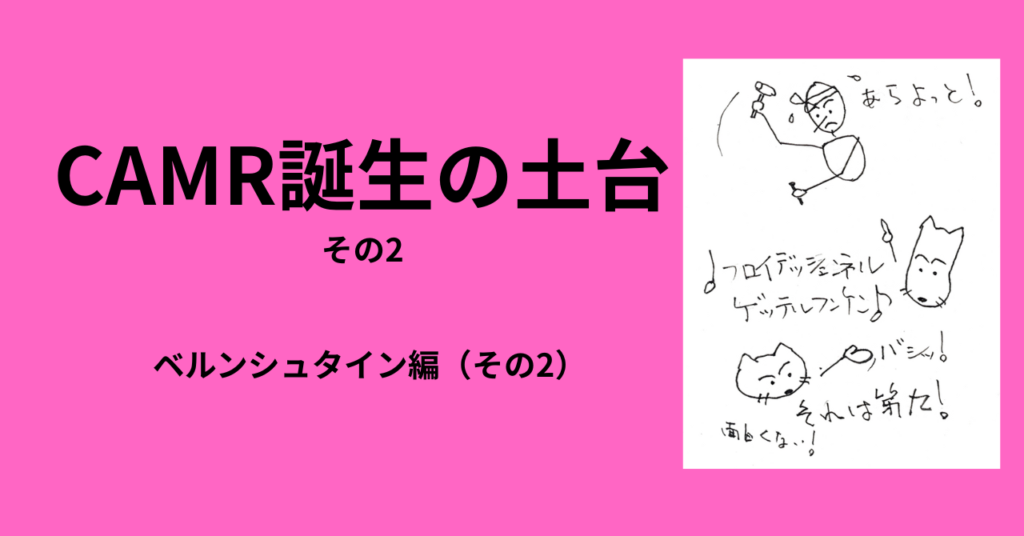CAMR無料勉強会のおしらせ 「CAMRのアプローチ編」
学校で習う人の運動システムは、身体の構造と各器官の働きで理解します。
もし運動に問題が起きると、構成要素(筋力や柔軟性、持久力、感覚、認知など)を調べ、悪い構成要素を原因として想定します。つまり因果関係を想定します。
たとえば歩行が不安定だと筋力などを調べて、下肢の筋力低下を発見するとこれを歩行不安定の原因として因果関係を想定します。そして下肢の筋力強化を行うわけです。
CAMRでは、人の運動システムは構造ではなく、作動の特徴で理解します。たとえば筋力は運動リソース(運動の資源)です。筋力は単に力に過ぎないので歩行という運動を成立させることはできません。筋力をどのように利用するかという運動スキルこそが運動を成すことができるのです。
それで重要なのは運動スキルをどのように身につけ、修正するかという運動スキル学習が大事です。ただ整形疾患などでは、傷害が局所的で他の身体部位の働きが失われることはありません。それでセラピストは筋力などの運動リソースを改善するだけであとは患者さんが勝手に動いて運動スキル学習をしてしまうのです。それで整形領域では「運動スキル学習」はあまり重要視されなかったのです。
でも脳卒中などでは障害部位が広範囲で体の多くの働きが失われてしまいます。自分で動けないので、運動スキル学習にはセラピストの助けがどうしても必要です。
そこで以下の通りCAMRの無料勉強会を実施する予定です。興味のある方はドンドンお申し込みください。きっと仕事が楽しくなりますよ(^^)
今回のテーマは「CAMRのアプローチ編」です。講義の最初に、「理論編」、「評価編」のまとめをやりますので、初めての方でも大丈夫です。
《CAMR無料勉強会の詳細》
日時:2026年3月15日(日曜日)9時30分~13時頃まで。
場所:東広島市芸術文化ホール くらら 2階 203研修室6(東広島市西条栄町7-19 )
講義準備
・簡単な実習がありますので、動ける服装が良いです。
・もしあればお手玉を三つ持ってきて頂けると良いです。こちらでもある程度の数は用意しています。
・講義ノートはPDFファイルで勉強会の一週間位前には配付する予定です。
申込み方法
申込み方法:氏名・職種・経験年数を記入。以下の◎をアットマークに変えてメールしてください。
camrworkshop◎mbr.nifty.com