異常歩行は誰の問題?その2
前回も述べたように、そもそも見た目の形ややり方が正常歩行から逸脱しているだけで、「異常」だと言ってしまうのは問題である。というのも「異常」という日本語としても非常に強い否定的、悪い意味の「ラベル」を貼ることになるから。
今回は患者さんの生み出した歩行、たとえば「ぶん回し歩行」は、実は正常な歩行の一種ではないか、と提案したいと思う。
そこでまずは健康な若者の歩行を観察してみよう。若者は明るく広い廊下を普通に歩いている。しかし真っ暗闇の中では両手を前に、そして片脚も前に出して彷徨(さまよ)わせて障害物を探しながら少しずつ進む。
人混みの中では、横向きに歩いて狭い隙間を進んだり、前から迫ってくる人を後に下がって横向きになり進路を譲ったりする。
健康な若者とは言え、いつも同じように歩いているわけではない。大好きな恋人に振られた直後は、背中を丸めて両肩を落としトボトボと歩く。逆に良いことがあると弾むように歩いたりする。前から怖い犬が来ると緊張してぎこちなくなる。
丸太の一本橋では両手を広げてバランスをとりながら横向きに、あるいは正面から綱渡りのように進む。
凍っている路面では、背中を丸めて足下を見ながら滑らないようにヨチヨチと進む。自然に両手がほんの少し前に出てバランスをとる。パーキンソン病の歩行の形にも似ている。
浅いが広い水溜まりがあれば、靴が濡れないようにつま先立ちになり、浅いところを探しながらつま先立ちで歩く。これは尖足歩行の形である。
田んぼの中を進むときは、片脚を泥から引き抜くのにやはり尖足の形になる。背屈位では泥から引き抜くときの抵抗が大きいからだ。さらにつま先まで泥から引き抜くために膝を高く挙げることになる。これは腓骨神経麻痺で下垂足があるときの鶏歩の形である。
若者の片脚に重い重垂ベルトを巻くと、最初は脚の力でまっすぐに振り出すが、やがて疲れるので体全体で振り出すようになる。これは片麻痺患者さんのぶん回し歩行に似ている・・・・ どうだろう、こうして見ると健康な若者は、環境や状況の変化に応じて歩行の形ややり方を適応的に変化させている。環境や状況の変化は無限にあるので、若者の歩行の形も無限に変化する訳だ。健常な若者の歩行なので全ての形が正常歩行と言えそうだ。
学校の教科書では、見た目で若者の平地での標準的な形を正常歩行と決めている。
一方CAMRでは、人の運動システムの作動の特徴に焦点を合わせる。そうすると上述のように人の運動システムには、「環境や状況の変化に応じて、形ややり方を変えて、 適応的に歩行の機能を生み出し、維持する」作動の特徴があることが分かる。
この作動の特徴はCAMRでは「状況性」と名づけられている。つまり正常歩行とは、歩行の形ややり方ではなく、「状況性」という作動の特徴を示しているかどうかである。
そうすると片麻痺患者さんは「半身に麻痺が起こるという状況変化の中で、『ぶん回し歩行』という歩行スキルを生み出して適応的に課題を達成するという状況性」を示しているとも言えるので、ぶん回し歩行はCAMRの定義では正常歩行の一種と言える訳だ。
次回はもう一つの作動の特徴からぶん回し歩行を評価してみようと思う。(その3に続く)
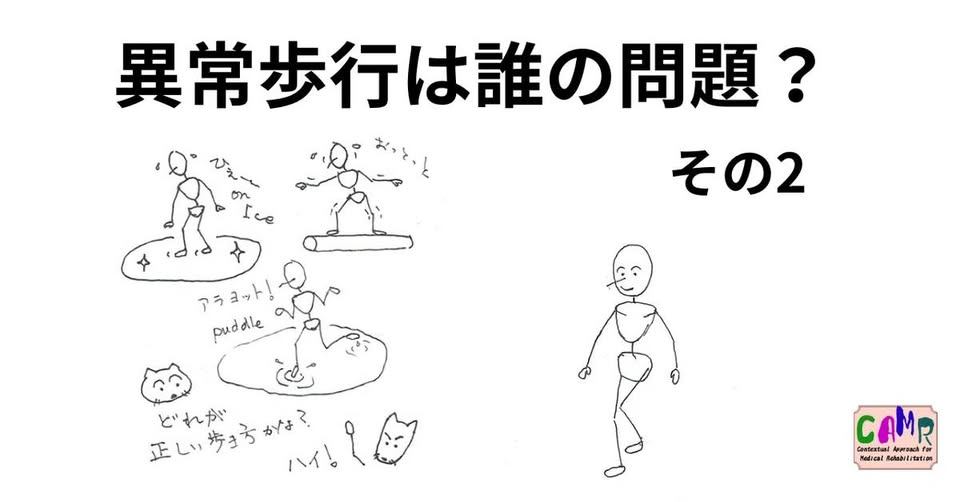


カテゴリ:異常歩行は誰の問題? [コメント:0]














コメントフォーム