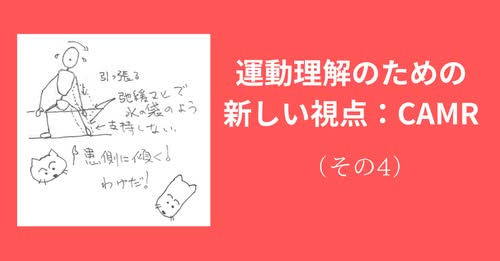人の運動システムには「なんとか問題を解決して課題を達成するために、自律的に身体の内外に利用可能な運動リソースを探し、問題解決と課題達成のための運動スキルを生み出して、必要な課題を達成しようとする」性質がある。
これはCAMRでは「自律性」と呼ばれる作動の性質である。
この作動の性質は、たとえ障害が起きても変わらずに作動する。問題を解決して必要な運動課題を達成するというのは、運動システムのもっとも基本的な作動だからだ。もし仮にこの作動の性質が見られないとしたら、人の運動システムとしては崩壊していると言える。
脳卒中では発症直後に弛緩麻痺が見られる。弛緩状態の体というのは、可動性のある骨格が水の袋に入っているようなものだ。プラスチックの袋に水を入れてテーブルの上に置くと重力に押されて安定するまで広がろうとする。弛緩状態の体もそんなことになる。不安定に揺れながら安定するまで広がろうとする。
そして健側の体を常に患側に引っ張り続ける。常に揺れて体全体を不安定にする。体重を支えたり重心を移動したりすることができない。これでは体を安定させたり、動いたりすることができなくなる。
それで運動システムは自律的に問題解決を図る。弛緩状態の部位の筋肉を硬くするわけだ。身体の内部に筋肉を硬くするためのメカニズムを探して総動員する。
傷ついていない脳幹から下のレベルでコントロールされる伸張反射や原始反射を亢進させることで、少しでも筋肉に収縮を起こそうとする。また筋肉自体にはキャッチ収縮というメカニズムがあってエネルギー消費無しに収縮状態を維持することができる。これを強めて筋肉を硬くする。
硬くなると体重を支え、重心移動のための支点もできる。これで動くことが可能になる。あるいは硬くなって塊となった上肢は揺れることなく健側の体についてくるようになる。それで動けるようになるわけだ。
CAMRでは、体を硬くするのは障害後の弛緩状態という問題を解決するための運動システムの自律的な問題解決であると理解する。これはCAMRでは「外骨格系問題解決」と呼ぶ。筋肉を硬く固めて、カニや昆虫などの外骨格動物のようにそれで支持を得るからだ。
だが、これで「めでたし・・・」とはいかない。この問題解決は、あり合わせのメカニズムを使った急場しのぎの対処である。抑制が利かない。次第に過剰に繰り返されるようになる。体は徐々に硬くなって、運動範囲を小さくしてしまう。硬くなった筋肉は抵抗になり、動く速度が遅くなる。あるいは動くためにより努力が必要になる。ちょっとした運動でも発熱、発汗、息切れが見られるようになる。
さらに過剰に繰り返されると硬く成りすぎて動けなくなってしまう。あるいは不快感や痛みなどが見られるようになる。
初期には問題解決の作動だったのに、次第に新たな問題を生み出して患者さんを苦しめてしまう。このように問題解決が新たな問題を生み出してより悪い状況を作り出すような問題解決を、CAMRでは「偽解決(psuedo-solution)」と呼ぶ。
実はこの偽解決が患者さんの障害による状況をかなり悪くしている。偽解決状態を改善するだけで患者さんの持っている隠れた運動能力が発揮されやすくなってくる。
これら伸張反射や原始反射の亢進や筋肉が硬くなって過緊張状態になることは、Jacksonの階層型理論では脳性運動障害の症状として理解されていた。
Jacksonは陽性徴候の原因は、中枢神経系の上位レベルの下位レベルの解放現象として説明した。それで治療方針としては、上位レベルの機能を回復するという方針を持つ。壊れた脳細胞の再生を目指したり、壊れていない脳細胞にその機能を再学習してもらったりしようとするわけだ。
この考えは日本に入って60年近く経つが、未だにそれがなされた、成功したという科学的報告はない。きっと実現不可能な方針なのだろう。
さて、CAMRでは外骨格系問題解決によって生まれた筋の硬さは、障害後の運動システムの問題解決の作動によって生まれた状態である。症状そのものではない。それでその過緊張状態という偽解決状態を改善することは可能である。
たとえば上田法という徒手療法がある。(その4に続く)
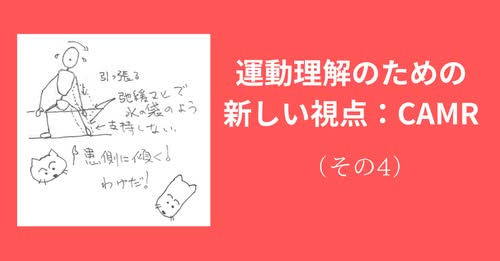



≧(´▽`)≦
みなさん、ハローです!
「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。
今回は「ADLは介護問題!その3」です。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆
ADLは介護問題!その3 2014/2/6
~悪循環・良循環~
秋山です。
先日のベーシックコースで多くの示唆をいただきました。今回の投稿もその影響有り、です。始まり、始まり・・・
AさんのADL(能力)は変化しませんでしたが、生活問題は解消しました。これは、「機能はプラトーだから用具を工夫」というリハビリでお馴染みの解決方法とは違います。Aさんの状況変化をもう少し見てみましょう。
以前の問題はなんだったのか?
尿失禁→介護量が増えて家族もイライラ→Aさん萎縮→尿失禁が続く・・・という悪循環にはまっていました。ご本人にとっては尿失禁がもちろん直接の原因ではありますが、それに続くこの悪循環(家族への申し訳なさなど)がこの問題を更に大きくしていました。
尿失禁をなくそうとするアプローチやポータブルトイレを使う練習は効果がありませんでした。これらのアプローチは「頑張ってもうまくいかない」という結果に終わり、むしろ悪循環を強めてしまいます。自分ではコントロールできないことを「自分で解決しなさい」というアプローチはむしろ悪循環を強めてしまいます。(これらのアプローチが「偽解決」です。詳しくはHPなど)
さて、ここでこの悪循環を断ち切る手段になったのは、視点の転換でした。目標は「尿失禁をなくす」ではなく「この悪循環を断ち切る」に変えたのです。介護職の努力により、「失禁しても衣服の汚染がない」という状況を作り出し、結果介護量が減りました。実はこれは「ブリーフセラピー(短期療法)」の応用です。HPを参照ください)
このアプローチにより、実際に深夜の介助はなくなり、洗濯物も減少しました。この変化は家族のゆとりやご本人の自信につながり、日中排泄の失敗も減って、良循環に入ったのでした。めでたし、めでたし・・・
★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆
【CAMRの基本テキスト】
西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版
【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①
【CAMR入門シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①
西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②
西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③
西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④
西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!



≧(´▽`)≦
みなさん、ハローです!
「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。
今回は「リハビリは、1回20分の訓練で何ができるのか?(その3)」です。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆
リハビリは、1回20分の訓練で何ができるのか?「その3」
「その1」では、リハビリスタッフこそが「運動余力」を最も有効に改善できる専門家である、と述べました。また「その2」では「運動余力の改善」と「従来の運動機能改善」とは違っていることを説明しました。
さて、では実際に運動余力の改善はどう行うか?一つにはクライエントの希望に沿った運動課題を工夫していくことです。人は適切な運動課題を通して、必要な運動リソースを豊富にし多様な運動スキルを発達させることができます。
もう一つは柔軟性を徒手療法で変化させたり、環境調整や自助具、介助者のシステムなどを持ち込んだりと運動リソースを直接変化させることです。さらに痛みは運動リソースやスキルの出現を邪魔するので、可能なら痛みの軽減を図ります。こうして構成要素間の関係と運動リソースの両方に同時にアプローチします。
この視点に立ってクライエントに接するうちに、以下のことに気がつくようになりました。
- クライエントは見た目以上に沢山の「隠れた運動余力」を持っている。が、クライエント自ら動くまではこれらに気がつかれないことが多い。
- 良循環と呼ぶべき状態がある。急性期や軽度のクライエントでは、ほんの少しの運動課題達成の経験によって、「隠れた運動余力の発見→活動の多様化→更なる運動余力の改善・・」といった良循環に入ることが多い。
- 逆に「袋小路」と呼ばれる状況に陥るクライエントも多い。「偽解決」や「貧弱な解決」をひたすら繰り返し、「隠れた運動余力」に気がつかれない。脳性運動障害や高齢者などのケースが多い。セラピストには、袋小路からクライエントを救い出す知恵と工夫が必要である。
- 急性期に、運動余力の改善を図らないでいきなり歩行のような動作訓練を行うと、貧弱な解決(たとえば患側下肢支持期の膝伸展ロック)のような安易な方法を取ってしまうため、袋小路に入りやすい。
20分という時間は少ないものの、運動余力の探索と改善に焦点を絞り込むことで、リハビリ訓練の効果を生み出すことができます。(詳しくは講習会で・・・・)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!



≧(´▽`)≦
みなさん、ハローです!
「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。
今回は「CAMRの簡単紹介(その4)」です。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆
その4 根本的な解決を目指すのか、その場その時に達成可能な目標にアプローチするのか?
従来型のアプローチは、問題があるとWhyという疑問から始め、より根本的な原因を求める。そしてその原因そのものにアプローチしようとする傾向がある。もちろん根本的な原因にアプローチするのだから、根本的な解決法と考えられる。根本的解決! 万歳!
もちろん根本的な解決が図れるケースもある。しかし常に根本的解決が優れているからこれを闇雲に目指す、というのは実はとても危険である。根本的な原因の解決不可能なケースも多い。たとえば麻痺や小脳失調など。根本的な解決を目指すと、しばしば偽解決やユートピア・シンドロームの罠にはまってしまうことがある。(HPをご覧下さい)
これを防ぐには解決可能な原因かそうでないかを見極める知識と経験が必要で、そしてなによりも常に根本的な解決が優れている、という思い込みを見直すことだ。たとえば失われた機能を取り返す、という目標は本当に取り戻せるなら素敵だが、本当に取り戻せるのか?そのために今を犠牲にするのはどうだろう?
CAMRでは、常に焦点を今この場でできることに当てている。今この場でできることの積み重ねが、よりできる未来へつながる道ではなかろうか?いつ達成できるか分からない根本的な解決のために、今はできなくても仕方ないと諦めることはしないのである。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!