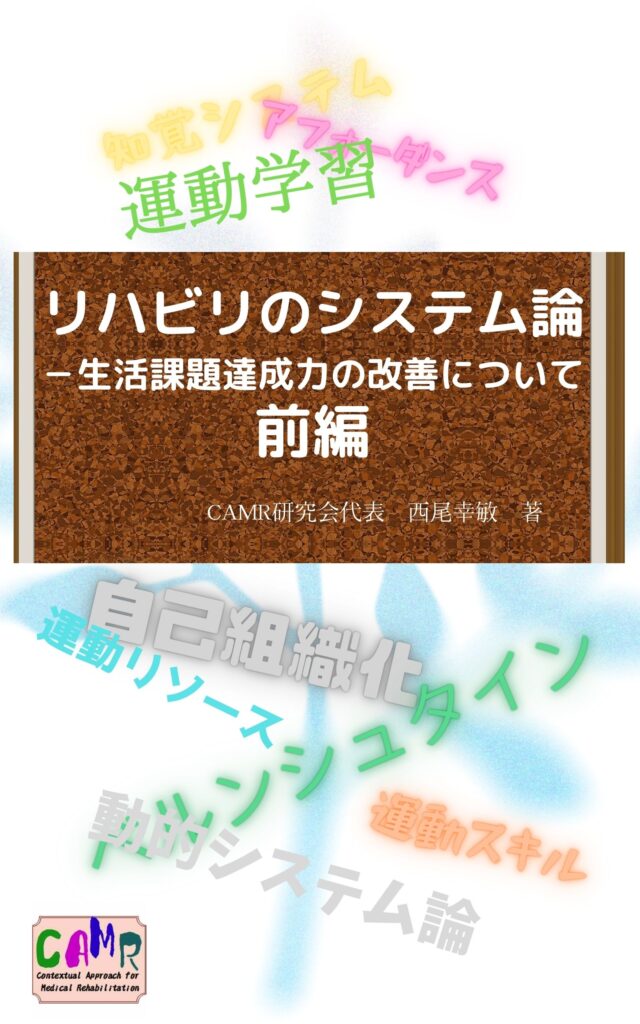臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!
CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!
人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!
詳細はこちら
CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!
講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!
詳細はこちら
CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!
基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!
詳細はこちら
「歳のせい」と言う勿れ を読む!その4
「セラピスト主導」の反対は「患者主導」ではないのだ⁈
寒いです。炬燵を出したい秋山です。
CAMRの治療方略の中に、「クライエント-セラピスト協同治療方略」というのがあります。私には特に思い入れのある考え方で、CAMRの根幹にかかわるものと思っています。個人の感想です。
ほとんどのセラピストは患者さんを下に見ていないし、「セラピストが主導します」とも思っていないでしょう。患者さんの思いに寄り添って何とかしてあげたいと一生懸命です。ですが、この「一生懸命」が患者さんを置き去りにしてしまうという危険をはらんでいるのです。
「セラピスト主導」を反省して、主導権は患者さんにあるというのは一見発想の転換にみえますが、実はコインの裏表です。どちらか一方の答えに従うという点では同じ枠組みと言えます。主ー従が反転するだけです。
「セラピスト主導」を改めるのならば、患者さんとセラピストがそれぞれの立場で協同して事に当たる枠組みへシフトするということになります。
患者さんとの協同という考え方は、医療界全体でもだいぶ浸透してきているようですが、どうもうまくいかない時がある。その要因の一つに、「正しい答えは専門家であるセラピストが持っている。持っているべきである」という信念が抜けきれないということがあります。患者さんの話をよく聞いて、患者さんが納得して訓練に取り組めるよう一緒に工夫しあっていても、根本がセラピストの答えなのなら、そしてそれを患者のためと一生懸命にやればやるほど患者さんが置き去りになってしまうことがあります。
次回に続きます。
【CAMRの最新刊】
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」
【CAMRの基本テキスト】
西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版
【あるある!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」
【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①
【CAMR入門シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①
西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②
西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③
西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④
西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!



日曜だけど木曜日のつぶやき 3
(木曜に投稿したつもりだったのですが、アカウント間違いで遅延しました・・・)
「歳のせい」と言う勿れ を読む!その3
腑に落ちると、自分のものになる⁈
今朝あわてていて、履いた靴下の指先がちょっと薄い…。ハラハラドキドキだった秋山です。訪問なので、靴脱ぐんです。今日の内容はリメイクです。焼き直しです。自分の過去の投稿が元ネタなので、パクリではないです(^^;)
10年近く前に、「CAMRの旅 お休み処」という用語や概念のミニ解説シリーズを書きました。CAMRは日々進化しているので、ちょっと合わなくなってきているものもありますが、今も昔も変わらないものを再掲します。
CAMRの旅 お休み処 その3
「人は生まれながらに運動問題解決者2 ~では、セラピストは?~」2013/1/24 (抜粋)
CAMRで言う「自律した運動問題解決者」は、セラピストに対しては道徳的なスローガンではありません。抽象的な概念を努力目標として据えているのではなく、専門職としてクライアントが主体的に動ける状況を具体的にどう作るかを問うものです。
「実践から生まれ、実践に役立つ」所以です。
書いてしまうと簡単そうですが、現実には、「クライアントのために」されていることがクライアントを置き去りにしてしまっていることは少なくありません。言葉での説明だけでは不十分で、クライアントが実感できる、自分の文脈の中で腑に落ちた時に、いきいきと課題に取り組まれます。(以下、略)
運動が続かない患者さんを「やる気がない」「依存的」というのは簡単ですが、常に前向きで意欲的なのが当たり前ではありません。必要性を理解していれば継続して実践できるはず、というわけではないのです。
と言っても、患者さんは何もできない、やろうとしないものだというわけでもありません。問題を解決しようとするけれど状況が変わってこれまでの方法では上手くいかず困惑している状態です。
最近は「黙って俺についてこい」的なセラピストは少ないと感じます。大抵の場面で患者さんに納得してもらってやる気を引き出して・・・と頑張っています。
ただ、「説明と納得」にとらわれると、言語的に正しく理解させようという姿勢になりがちです。これは困惑している患者さんには良い手ではないことも多いです。ちゃんと理解される方ももちろんおられます。正確な理解というより、理詰めの説明が肌に合う場合もあります。無自覚にしてもセラピストの枠組みで理解するということを患者さんに強いていることはないでしょうか。
次回は患者さんが自分の枠組みで腑に落ちるような技術、クライエント―セラピスト協働治療方略についての予定です。できるだけ具体例を入れるようにと思うのですが、今回は抽象的でつまんなかったですね、反省。
【CAMRの最新刊】
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」
【CAMRの基本テキスト】
西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版
【あるある!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」
【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①
【CAMR入門シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①
西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②
西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③
西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④
西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!



木曜日のつぶやき 2
「歳のせい」と言う勿れ を読む!その2
「褒める」は上から目線⁈
最近、褒められた覚えのない秋山です(^^;)
「褒める」でググると出るわ出るわ…。今の世の中、褒めるは重要なキーワードのようです。CAMRでも褒めることを推奨しています。ですが、いざ褒めようとすると意外と難しい。特に仕事上、年上の方に対してとなるとなおさらです。
難しさの一つに「偉そうな言い方になっていないか心配だ」があると思います。
患者さんを褒めなくちゃと思うのだけど、どう言っていいのかわからない、「若造が偉そうに」と思われないか?「子ども扱いしおって」と思われないか?できてないのに無理矢理こじつけになってないか?考えれば考えるほど、難しく思えてきます。
CAMRにはコンプリメントという技術があります。
complimentは「ほめ言葉」と訳されますが、ここでは「ねぎらう」と言った方が理解しやすいと思います。結果を褒めるというよりも、過程をねぎらうということですね。結果を褒めてももちろん良いのですが、こちらが判定を下しているという枠組みにはならないように注意したいです。
実際、患者さんは難しいことに取り組んでいるわけで、楽ではないですよね。「難しいのによく頑張られましたね」「今日もしっかり運動されましたね」など、苦労をわかっていますよと伝えられると「わかってくれている」と患者さんも思える。上手くできた時は「やりましたね!」と一緒に喜ぶスタンスなら無理なく言葉にしやすいのでは。コンプリメントには「丁寧なあいさつ」という意味もあるそうですよ。
アドラーは、よくできたと褒めるのではなく、ありがとう助かったと感謝を述べるのだ、と言っていますが、まあ、あまり背伸せず、今できることを確実にやっていきましょう。
「またうまいこと言って」と言われてもニヤニヤしてくれてたら、ありですかね。「心にもないことを言って」とムッとされたら言い方を考え直してみましょう。
みなさん、今日も1日お疲れ様でした。よく頑張りましたね!難しいことも最後までやり切りましたね!忙しい中、読んでくださりありがとうございます!
【CAMRの最新刊】
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」
【CAMRの基本テキスト】
西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版
【あるある!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」
【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①
【CAMR入門シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①
西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②
西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③
西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④
西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!



日本勝ったぜ!万歳!! -状況変化の戦術を考える!(サッカーワールドカップに関してのCAMRの緊急エッセイ)
西尾です。サッカーは素人ですが、問題解決にCAMRという状況変化アプローチを勧めている人間としてドイツ戦、とても面白かったのです(^^)
今回はドイツ戦を状況変化アプローチの視点から考えてみたいと思います。
まずは試合の経過を振り返ってみましょう。
前半ドイツは上手く攻めて日本のハイプレスが機能しません。ずっと攻められ続けましたね。結果として守備に消耗され、1点先取され、攻撃がほとんどできない状態でした。守備はそれでも何とか抑えていましたが、ハイプレスからの守備と攻撃が日本の中心戦略なので、それはまったく機能していませんでした。
前半のこの状況は、ドイツの計画通りと言えます。ボールは比較的多くドイツのミッドフィルダーの作る網の中にありました。日本は押し込まれていたので、ボールを奪っても出しどころがなくやはりドイツミッドフィルダー網にボールが引っかかってしまう状況に落ち着いた訳です。
もちろん日本側としては後半に向けて大きな状況変化を図らないといけません。これははっきりしています。そうしないと負けることは明らかです。
さて後半、実際、森保監督は状況変化を図ります。
最初のアプローチは小さなものでした。ミッドフィルダーの久保一人を下げて守備の富安選手を入れるだけです。
しかしこれは戦術の変化を伴います。4バックから3バックへ。そしてより敵陣に近いところで積極的に守備ができる人数を増やして、ハイプレスとそこからの攻撃をより効果的に行えるようにするためでしょう。
これは最初からある程度予定されていた戦術変化かもしれません。
その結果、後半から少しずつ日本ペースになります。
一方ドイツの監督は前半が良かったので、状況変化は起こしたくなかったはずです。つまり戦術がうまくいっていたのでそれは変えたくなかったはずです。
でも徐々に小さな変化が起きます。ドイツ監督はこの状況変化の要因を、ドイツのミッドフィルダーの疲労だと考えたのでしょう。後半22分にベテランのミッドフィルダー二人を交代させます。
実はこのドイツ監督の最初の判断とアプローチが、ドイツ敗戦の一つの要因となったと考えられます。ドイツ監督は、この状況変化の要因を日本の小さな選手交代と戦術変化ではなく、ドイツ選手の疲労と考えてしまった訳です。もちろん疲労は間違いなく一つの要因でしょうが、もっと大きな状況変化のきっかけである戦術変化に対応することが遅れました。
状況変化が起きた場合、その変化を起こしたきっかけの要因を見つけて判断する必要があります。この変化を起こすきっかけの要因は、動的システム論では「コントロール・パラメータ」と呼ばれます。
この視点から考えると森保監督の采配は素晴らしかったのです。もし後半最初から富安だけでなく、三苫、堂安、浅野などの攻撃的な選手を1人でも投入していたら、ドイツ監督もすぐに状況変化のコントロール・パラメータは、日本の戦術変化と攻撃的な選手の投入であると判断して、戦術的な対応を図ったはずです。
しかし変化のきっかけは1人の守備選手の交代という地味なものでした。もちろんスリーバックへの戦術変化はあるものの、ドイツ監督としてはしばらくその経過を見守るしかなかったのでしょう。
森保監督は一見小さな変化から始めました。そしてこれによってその後のドイツ監督の戦術変化への対応が遅れてしまったのです。またその後、段階的に攻撃的選手を投入して、雪崩のような大きな変化に繋がる状況変化を起こしたのです。
こうして日本は優勝候補ドイツに勝利しましたとさ!めでたし、めでたし・・・
さて、この他にもこの試合には僕達リハビリのセラピストにとっても治療方略や状況変化のアプローチを考える際のヒントがいくつかありました。ワールドカップが終わったら、じっくりと考えてみたいと思います。(ワールドカップの緊急エッセイ終わり!日本チーム、素晴らしかったです!次も頑張れ!(^^;))

【CAMRの最新刊】
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」
【CAMRの基本テキスト】
西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版
【あるある!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」
【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①
【CAMR入門シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①
西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②
西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③
西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④
西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!