「悪いところを見つけて治す」以外の発想(その2)
「立ったまま靴下を履いてみましょう!」というと、多くの人が片脚立ちになり、支えていない方の脚を大きく屈曲させて、両手で持った靴下を履く動作をする。
中にはバランスを崩して、すぐに履けない人もいる。そこで「どうしたら立ったまま安定して靴下を履けるようになりますか?」と聞くと、大抵のセラピストは、「下肢を鍛えたり、片脚で様々な重心移動の練習をしたり、体幹の筋力・バランスを鍛えたりするような練習をしたら良い」と答える。
学校で教えられた「身体の悪いところを探して、改善する」という視点がしっかりと身についているわけだ。確かに悪いところを見つけ出してそれを改善することで結果を出せるだろう。
この課題には、片足で立ってバランスをとりながら重心を保持する働きが必要で、下肢の支持性や体幹の柔軟性やバランス能力が劣っていると、片脚での靴下履きがうまく行かないと考え、それらを改善しようとしているわけだ。
前回これは、「機械を直す」という発想から来ているのではないかと説明した。機械を直すには、作動の様子からどこの部品のどの機能が悪いかを予想し、その部品を修理・交換すれば良いわけだ。
しかし人は機械ではない。人には人ならではのアプローチもある。たとえば「立って靴下を安定的に履く」は、「壁にすがって片脚立ちをしながら靴下を履く」ことでこの課題は達成できる。あるいは支持性が弱いなら、「片脚を少し前にして両脚で立ち、両手で靴下を持って前に出した方の足の前に持っていく。それから足のつま先を上げて靴下をかぶせ、今度は踵を浮かして靴下を引き上げる」やり方でも可能である。
「なあんだ、ずるい!片脚で立って履くのかと思うじゃないか!」と言われそうである。
しかし「立ったまま靴下を履いてみましょう」という課題である。特定のやり方を指定しているわけではない。
ロボットであれば、間違いなくプログラムされた特定のやり方で靴下を履くだろう。というより、その履き方しかできない。もしその履き方ができないなら、どこかに故障があるわけだ。だからといって、人でも特定のやり方に縛られる必要はない。
人は同じ課題でも状況に応じてやり方を変えるから。その時、その場で適切な運動スキルを生み出すことができるからだ。
更にリハビリでは、まず「生活課題の達成力を改善する」ことが大事ではないか。患者さんができるかどうかではなく、「特定のやり方をまず(正しい運動として)勧める」というのは、セラピストの価値観を押しつけるような気がして、どうもリハビリでは相応しくないように思う。
たとえば片麻痺後に分回し歩行で実用的に歩いている患者さんに、「その歩き方は正しくない。健常者のように正しく歩きましょう」というセラピストの価値観で特定のやり方という目標を押しつけるようなものではないか。
これが達成可能な目標ならまだ良いが、実際には麻痺を治すことはできないし、結果的に健常者の様に歩くこともできないので、達成不可能な目標を押しつけていることになる。
機械ではこれが正しい作動ということがはっきり決められているので、その正しい作動に戻そうとする。機械を基に考えていると、まずは人も体を治すことが基本になる。更に健常者の様に「正しい運動」をすることが目標になりやすい。正しい運動を勝手に仮定して、「(これが正しい運動だから)ただ課題が達成できてもダメ。正しい運動をしましょう」などということになってしまうのではないか。
でも人では課題達成の方法は無数に生み出される。どの運動が正しいかではなくそれぞれ異なった方法は状況に応じて選ばれるわけだ。適正な運動は状況に応じて異なるわけだから、どの方法が良いと一つに決めることはむしろナンセンスである。麻痺があれば麻痺があるなりに歩くことが当然だろう。
今回のように靴下を履く場合、筋力やバランス能力の代わりに両脚をついたまま柔軟性を用いて靴下を履いたり、壁などの環境リソースを利用して履いたりすることは、人では普通に見られる。
これはCAMRでは、「同一課題の運動リソース交換可能性」と呼ぶ人の運動システムの作動の特徴である。「立って靴下を履く」という同じ一つの課題は、状況に応じて様々な異なる運動リソースを置き換えても、その都度その利用方法である運動スキルを生み出して課題達成してしまうという性質である。
そうすると課題達成は、「原因と思われる身体リソースを改善するだけでなく、他の身体リソースを置き換えたり、環境リソースを利用したりしても可能である」と考えることができる。この視点を持つだけでも、状況に応じたより柔軟なリハビリ方針と手段を提供するための柔軟な思考を持つことができるのである。(その3に続く)
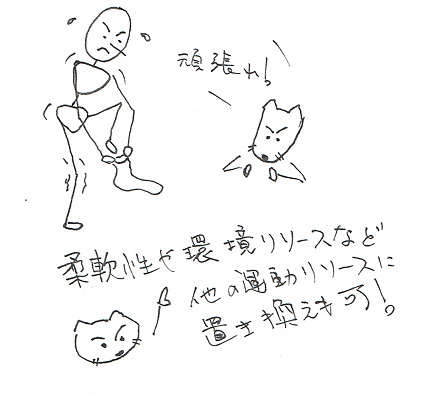
【CAMRの最新刊】
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」
【CAMRの基本テキスト】
西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版
【あるある!シリーズの電子書籍】
【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①
【CAMR入門シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①
西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②
西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③
西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④
西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!
















コメントフォーム