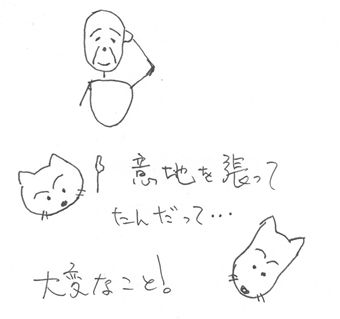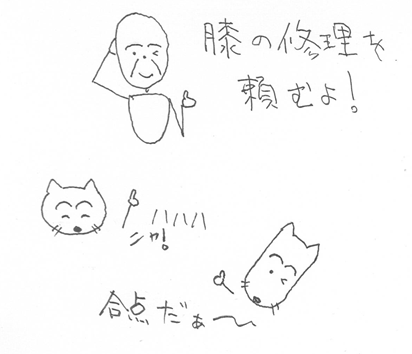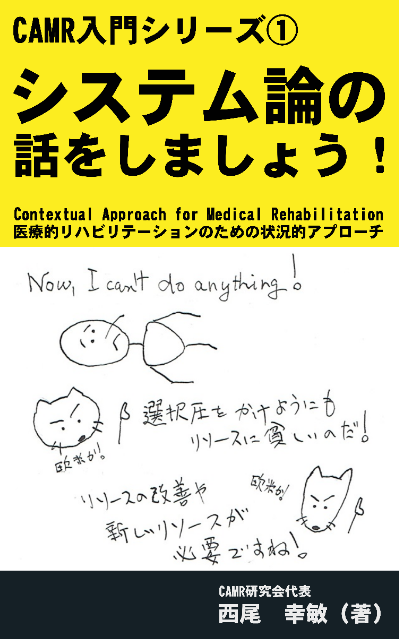臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!
CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!
人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!
詳細はこちら
CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!
講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!
詳細はこちら
CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!
基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!
詳細はこちら
こんにちは、CAMR副代表の秋山です。
「そんな役職あったんか 」と思われるでしょう。私も忘れかけていましたが、まだあったようです・・・。西尾代表のお留守の間、私なりのCAMRの見方をアップしてみます。と言っても、かなり前の投稿の再掲です。お付き合いいただけると幸いです。
」と思われるでしょう。私も忘れかけていましたが、まだあったようです・・・。西尾代表のお留守の間、私なりのCAMRの見方をアップしてみます。と言っても、かなり前の投稿の再掲です。お付き合いいただけると幸いです。
CAMRの効用 その1 ※個人の感想です(^^;)
OTの秋山です。CAMRがどんなものか話を聞いていただいた後、「おもしろい」「新しい視点を得られた」といった感想をいただくことが(よく!)あります。嬉しいことです。
ただ、「では、どう使うか」となると、もうひと山あるようです。CAMRが読み物として面白いに留まらず、臨床で役立つように、身近な例を挙げてみました。
その前に、CAMR初心者が戸惑いやすい、誤解しやすい点を挙げてみました。
まず、「原因を追究しない。システムの作動をみる」という点です。言葉ではわかっても、では実際の目の前の患者さんの何を見ればいいのか?目に見えないシステムを想像するのか?でも、それって正しいのか?構成要素をどんどん細かく見ていき、正常との違いを探していく方法に慣れた身にとっては、難しいところです。
もちろんCAMRでも、動きをみます。歩行なら振出しはどうやっているか、重心移動はどうか、などなど。
その見方が、「正常からどれだけずれているか」というのは、従来のセラピスト目線の見方。CAMRでは「運動システムはどうしようとしているか」という運動システム目線で内部からの見方となります。「うーん、わかるような、わからないような」、かもしれません。まぁ、「運動システムの視点で見る」ということを頭の片隅に置いて、症例を見ていきましょう。
訪問リハでの症例です。10年来の右片麻痺、自宅室内は短下肢装具+一本杖歩行で自立、屋外は見守りの方。普段は最小限の室内移動しかしないので、屋外歩行機会を持ってほしいということで訪問することになりました。
実用的に歩かれていますが、これまでのリハビリで「右足をまっすぐ出すように」とずっと言われていていたけど、ずっとできなくて、それが「悩みの種。ちゃんと足を出して歩きたいけど、難しい」と言われていました。
この方に対し、実用的に歩けているのだからリハビリに固執させてはいけない、「十分に歩けていますよ。細かいところを気にするより、やりたいことの目標をもって、どんどん外出しましょう」というアプローチも1つの方法だと思います。
ですが、これでは本人が望む動作の変化は無視して、価値観の変化を求めることになります。
それで患者さんが納得されることもありますが、いつまでも不満足なままということもよくあります。
また、正常に患側下肢が振り出せるようにセラピストの監督下で徹底的に反復練習するという方法もあります。この方は今までそういう訓練をされてきたので、さらに私がやっても改善する気はしない…。麻痺が治る、とは思えません。
これらの見方が、「セラピスト目線」です。「細かいことは気にしない」も、「正常歩行に近づける」も、セラピストが考えていることです。CAMRは、これらのアプローチとは違う視点で、別の方法を提案するものです。
「患者さんの運動を、運動システムに視点から見たらどうだろう?」
その2に続く




CAMRは状況変化の技法?(その7 最終回)
Aさんはその3週間後に、自分の脚と杖で歩いて退所されました。まだ膝が痛むことはあるものの、痛みなく歩けるコツが少しずつ分かってきたそうです。
さらにAさんはご家族がいくら言っても聞いてもらえなかった紙パンツと尿パッドを付けての退所でした。
もちろん根本の原因である頻尿・失禁の問題は解決していませんが、元々それが私達の仕事ではありません。ご家族の要望通りに「失禁が大変負担」という問題を解決することが目標でした。
以前は尿失禁のために、毎日たくさんの洗濯物や毎回のトイレ掃除だけでたくさんの労力と時間を費やしていたそうですが、これ以降は全く問題がなくなったそうです。
ご本人さんは問題解決に向けて、皆にアドバイスを求めて、結局、骨盤底筋や腹横筋の筋力強化もやられるようになりました。「単に尿を止めるために締めるだけでなく、尿をたくさん出し切ることも大事だろう」とAさん自身が計画を立てられたので、それに応えてトレーニングを計画しました。
もともと機械の設計をしておられただけに論理的で現実的です。もちろんすぐに効果は見られていません。退院後に、ご家族が希望されていた泌尿器科の受診もされるとご本人が決められました。
どうも後から分かったことですが、Aさんは元々普段から妻が一方的に受診だの、歩けだの、施設でトレーニングだのとうるさく繰り返すので、それに対する反発がこじれてしまったようです。僕に対しても「妻は一旦言い始めると制御ができなくて、言い続けるから嫌になるんだ。だから妻の言う通りには絶対になるまいと意地を張っていた」と笑われていました(^^;))僕もそこは素直に共感しました・・・なんてウソです、僕は妻にはそんなこと思ってませんからね(^^;)
今回は、ユニットでの介護問題の解決がリハビリでの訓練拒否問題の解決にも繋がりました。Aさんとの経験で、僕たちのリハビリドック・チームは自信を付けたと思います。いつも「起こせる状況変化を起こし、良ければ繰り返し、ダメなら他の状況変化を!」と考えます。
特に状況変化のやり方は無限に存在すると言っても良いのですが、今回のようにコミュニケーションのやり方を変化させる、コミュニケーションの立場を変化させることはとても有効であると気づかされました。これ以降は状況変化の第一選択に、コミュニケーション関係の変化を持ってくるようになりました。
今回のエッセイは、2017年発行の拙書「PT・OTが現場ですぐに使えるリハビリのコミュ力」西尾幸敏(金原出版)で掲載しなかったエピソードの一つに加筆・修正したものです。本書には老健のリハビリドック・チームの取り組みがいくつか紹介されています。
たとえば徘徊の認知症老人と職員のコミュニケーションを変化させることで徘徊の問題が解決した例や支配的な夫の一方的な介護関係で苦しんでおられた妻にとっての「言葉のやりとり」から「身体のやりとり」というコミュニケーションに変化させることで問題解決が行われた例、その他などが載っています。
興味のある方は是非ご一読くださいv(^^)
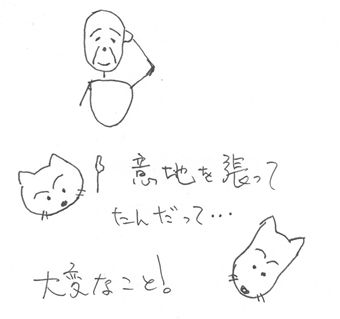



CAMRは状況変化の技法?(その6)
先週末のユニット内の出来事は月曜日の朝にリハビリにも知らされました。 Aさんが来られ、いつも通り最初に挨拶と短い会話をした後に、「あなたも困るだろうから、今日はマッサージでもしてもらおう」と言われます。ユニットの状況変化の流れがそのまま訓練室でも起きています。調子にのって、「運動もどうですか?」と聞きましたが、「運動はやらない」と言われます。それでも良い状況変化です。
早速車椅子からプラットフォームへ移ってもらいます。移乗から端座位へ、端座位から側臥位、背臥位へとなられますが、どうも動きが硬く顔をしかめたりされます。
初めて動いていただくと、体幹部の動きも悪く,痛みを我慢しながら動かれている様子です。まずは体幹部の筋膜リリースをしながら上田法の体幹法という手技を実施します。その後、起き上がってもらいます。
「では起き上がって車椅子に座ってみましょう」と勧めます。「おう」と1人で何とか起き上がられます。車椅子に乗り移ると、ご自分から話されます。
「僕は動くと体の色々なところが痛いんだが、歳だから体の各部は劣化してもう良くならないと思っていた。でもたったこれだけのことでも動きやすくなるね。今は痛みもあまり感じなかったよ」と答えられます。
その「劣化」という言葉で、これまでのことが一気に頭の中で繋がります。 「Aさんは機械に関わってこられたから、自分の身体を機械のように考えておられるのかもしれませんよ。機械は劣化したら部品を交換するか作り直すしかありませんよね。でも人の体は違います。劣化するだけでなく、回復もするんです!」
Aさんは何も答えられません。焦ります、急ぎすぎたか?でもしばらく間を置いて「そうかもしれんな」と言われます。「関節は劣化していて、動くとますますすり減って劣化が進むと思い込んでた」と言われます。状況変化の流れはまだ続いているようです。
「リハビリで膝の痛みは良くなるかね?」と聞かれるので、「ええ、やってみないと分かりませんが、見たところ大丈夫だと思います」と答えます。「では、頼むかな。僕の膝の修理を!」と笑われます。
この後は、順調にリハビリが進むことになりました。
どうもご本人は痛い方の膝をかばう意識で、「劣化を防ぐためにあまり使わないように」歩かれていたようです。だから逆に「膝周囲に力を込めて膝関節を安定させて歩きましょう」と提案しました。最初は両手で平行棒を支えて、痛い膝の荷重時に「力を入れて膝を安定させる」つもりで荷重練習を行います。また痛みの出ないように、「軽い膝の屈伸運動やつま先立ち、step練習」などの運動スキル練習も行います。
最初は変化があるのかどうか分からなかったけど、一旦変わり始めると雪崩(なだれ)の如く変化することもある、と思ったものです。(その7 最終回に続く)
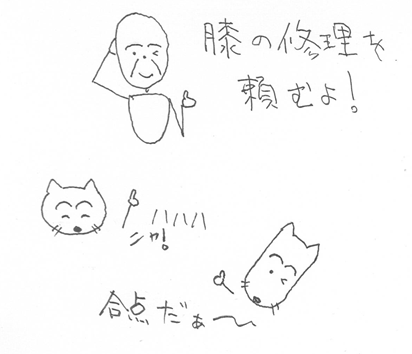



CAMRは状況変化の技法?(その5)
翌日5日目、介護主任がAさんと話し合います。この問題の解決はご本人さんの努力が必要で、そしてAさんはとても努力していることは分かっているということ。
だからAさんが問題解決の難しさは一番良く分かっている。だから私達もできるだけ解決策を提案しますから皆で協力しましょう。早く解決すればご家族も安心されるし、Aさんの希望通り、1ヶ月で退所できること。最後に「もし何か思いついたり、考えがあれば教えてください。皆で協力して解決しましょう。いつでも話しかけてください」と伝えたとのこと。
それに対してAさんは「特にない」と答えられたそうです。それ以降、介護士全員がAさんには「注意しない」ようにしました。
これまでは皆がAさんを世話する意識だったのですが、逆にその意識や態度を止めたのです。Aさん自身が問題解決者だからです。「我慢強くAさんからの指示を待つ」と話し合いました。
問題解決をAさんにお願いした5日目は、変化はなかったそうです。しかし6日目の土曜日に最初の変化がありました。Aさんをさりげなく観察していると、できるだけ長くトイレにいて色々されているということでした。一人で問題解決に取り組んでおられるようです。
そして介護士がトイレに呼ばれて行くとAさんが困っておられました。Aさんは便器に座ったまま、おしっこがしたたり落ちるタオルを持って固まっておられたそうです。どうも衣服を脱いでいるうちに、我慢できなくなって思わず首にかけていたタオルでおしっこを受けたようです。床を濡らさないように頑張られたのでしょう。
それでも予め打ち合わせた通りに「自分で考えて頑張られてたんですね」とコンプリメントをしました。それに対して「ごめん、他にやりようがなかった」と謝られました。謝られるなんて、とても良い状況変化の徴候です。
担当した介護士さんは,思わず「だから、皆が言ってるように尿パッドを使ったらいいじゃないですか」と言いそうになったけれど、すごく我慢してそれには触れなかったそうです。もちろんこの介護士さんの対応が後の状況変化を大きく決定づけたと思います。
彼女は、この経験を機に話をよく聞くようになったし、話すときに落ち着いて話す癖がついたと後から言っていました(^^)彼女自身の介護の仕事の転機にもなったそうです。
またAさんにとっても一人で問題解決に取り組むことの限界を悟られたのでしょう。
そのすぐ後Aさんは介護主任を探して自分から提案されたそうです。「色々やってみたが、やはり小さなパッドというのか、小さな板のようなおしっこを吸うやつを使った方が良いと思うのだが・・・」とのこと。
介護主任は心の中で小躍りしながら、「ああ、それなら良いものがいくつかあります。すぐに持ってきますね」と冷静に答えて、いくつかパッドを持って行き、選んでもらったそうです。
この日を境に、ユニット内での尿漏れ問題は大きく解決に向かいます。
でもまだリハビリ拒否問題があります。(その6に続く)




CAMRのYouTubeチャンネル、「カムラーの部屋」に新しい動画を投稿しました。見ていただけるとありがたいです。
今回のテーマは、テーマは「CAMR入門 その4 CAMRの運動問題の捉え方」です。以下のurlから。
「CAMR入門 その4 CAMRの運動問題の捉え方」
https://youtu.be/NiSMDfoBhn4e
CAMRのYouTubeチャンネル、「カムラーの部屋」



![]() 」と思われるでしょう。私も忘れかけていましたが、まだあったようです・・・。西尾代表のお留守の間、私なりのCAMRの見方をアップしてみます。と言っても、かなり前の投稿の再掲です。お付き合いいただけると幸いです。
」と思われるでしょう。私も忘れかけていましたが、まだあったようです・・・。西尾代表のお留守の間、私なりのCAMRの見方をアップしてみます。と言っても、かなり前の投稿の再掲です。お付き合いいただけると幸いです。