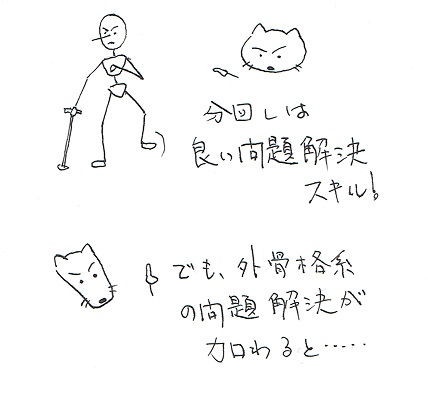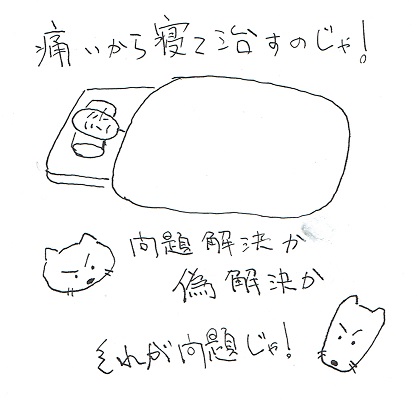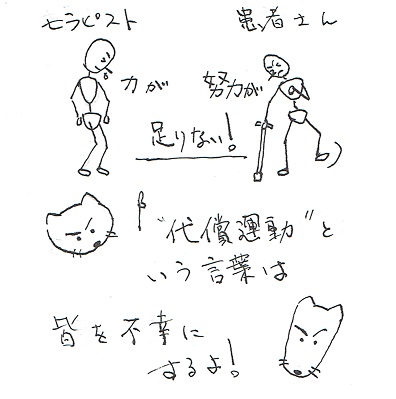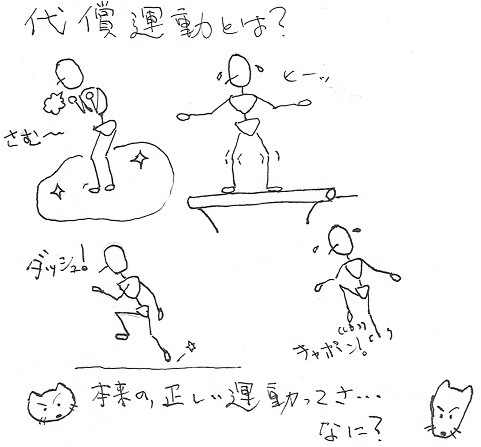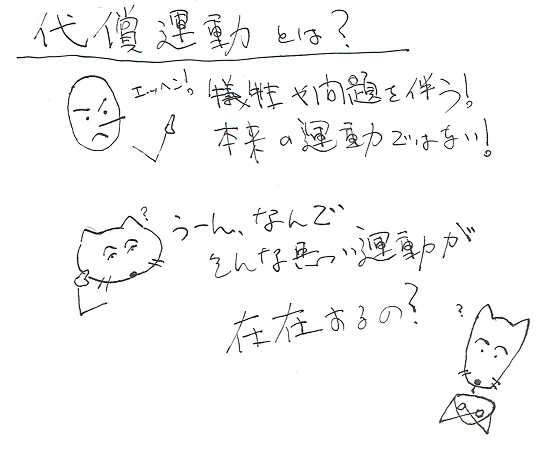臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!
CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!
人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!
詳細はこちら
CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!
講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!
詳細はこちら
CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!
基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!
詳細はこちら
「代償運動」って本当に悪い?(その5)
ここまでの流れ。
障害や運動問題によって新たに生じる運動は「代償運動」ではなく、本来「問題解決スキル」と呼ぶ方が正しい、と説明してきた。しかし運動システムのとる自律的問題解決にも「偽解決」が混じってくる。セラピストの役割は有効な問題解決と偽解決を見分け、偽解決の修正を図ることが重要、というところまで進んだ。
偽解決かどうかを見分けるためには、単純に見た目の運動の形に囚われるのではなく、総合的に様々な視点から患者さん自身にとってどのような新たな不利益があるかを考えていく必要がある。
たとえば片麻痺患者さんの分回し歩行を見てみよう。半身に麻痺があり、患側下肢を振り出すことができない。だから歩くためには非麻痺側の半身を使って分回しをする必要がある。
しかしそれに伴って新たな痛みや障害が発生することがあるだろうか?僕の経験ではあまりないように思う。つまり偽解決ではなく、半身麻痺のある体で上手く歩くための問題解決としてうまく成り立っているスキルである。
一方で脳性運動障害後に見られる身体の硬さは、CAMRでは「外骨格系問題解決」と呼ばれる問題解決スキルだが、しばしば偽解決が見られる。
たとえば片麻痺発症直後は、麻痺側の上下肢・体幹に弛緩性麻痺が見られる。弛緩性麻痺とは筋の収縮が得られないため、麻痺部の手脚は弛緩して水の入った袋のようになってしまう。重力に押しつけられて安定するまで広がろうとする。 このままでは動けないので運動システムは自律的な問題解決を図る。
つまり弛緩部分をシステム内の様々なリソースを利用して硬くしようとする。 たとえば伸張反射を亢進する。またキャッチ収縮のメカニズムを繰り返し作動させて弛緩部分を硬くしていく。キャッチ収縮は二枚貝の平滑筋でよく研究されている。一連の蛋白群の働きによって、エネルギー消費や電気活動なく筋の収縮状態を維持できる。そして脊椎動物の横紋筋でも同様の蛋白群の存在が確認されている。(最後に資料紹介)
硬くなれば荷重も可能になるし、1つの塊として引きずってでも動けるようになる。結果として身体を硬くすれば動くことが少しでも可能になるので、ドンドン硬くなる問題解決を繰り返すようになる。
しかしこれらは元々状況に応じて調整可能なメカニズムではない。抑制のメカニズムがないので繰り返され、ドンドン硬くなって柔軟性を失う。全身の運動範囲や重心移動範囲は小さくなって、かえって動きにくくなる。更に硬くなると変形が進み、固定化され、血流が悪くなり痛みや苦しみを生み出すという偽解決の状態を生み出すわけだ。
この外骨格系問題解決という問題解決スキルは、実は健常者の日常生活でもよく見られる。腰部ヘルニアで腰痛が出たときなどは、脊柱を側彎させてヘルニア部の圧迫を避けた状態で体幹を硬くする。
この場合、痛みが軽くなると自然に硬さは取れて元の柔軟性を取り戻す。ヘルニアのような整形疾患では上手く問題解決スキルとして機能しているわけだ。
だが脳性運動障害では麻痺は広範囲で継続する。従って外骨格系問題解決のスキルはずっと継続し、繰り返される。その結果として硬くなりすぎる。脳性運動障害では外骨格系問題解決スキルは偽解決の状態を生み出しやすい。
更にこの外骨格系問題解決が強くなると分回し歩行の動きを制限する。こうなると「分回し歩行は努力性の歩行でこのために体が硬くなる」などと2つの異なった現象が1つにまとめられて誤解されたりもする。困ったものである。問題をより複雑にするわけだ。
この硬くなりすぎるという偽解決の状態は、上田法などのHands-on therapy(徒手的療法)によって解決状態に導くことができるのだが、この詳しい内容はまた次回のココロなのだ!(その6に続く)
【キャッチ収縮に関する文献】盛田フミ: 貝はいかにして殻を閉じ続けるか?-省エネ筋収縮”キャッチ”の制御と分子機構. タンパク質 核酸 酵素 Vol33 No8, 1988.
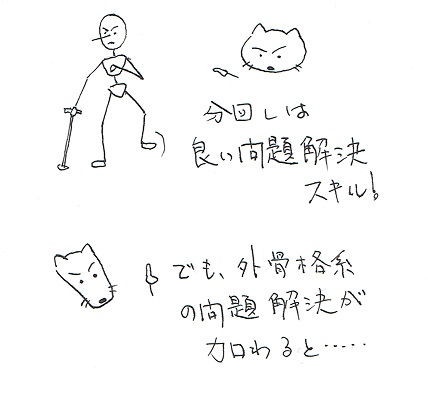
【CAMRの最新刊】
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」
【CAMRの基本テキスト】
西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版
【あるある!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」
【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①
【CAMR入門シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①
西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②
西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③
西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④
西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!



「代償運動」って本当に悪い?(その4)
これまでのまとめ。「代償運動」は「本来の正しい運動ではないので修正するべき」というイメージである。基本的に悪い運動であると考えてしまう。それでは運動システムの作動が目標としているものを表していない。
そうではなく障害後に生じる運動は、「運動システムが課題達成のために自律的に問題解決をするための運動スキル」である。だから『問題解決スキル』」という言葉で置き換えて使ったらどうかと提案した。
そうすると「人の運動システムって、機械と違って運動問題が起きて必要な課題達成が困難になると、自律的に問題解決を図って何とか課題達成しようとするんだな!機械とは違うんだな!」ということが自然に理解できるようになるはずだ。「ああ、やっぱり人の運動システムって素晴らしい!」と感じるのではないか。
ただしこれだけでは上手く説明できないところもある。このシリーズで最初に挙げたような、「足部・足関節が硬くて膝がバランスをとるために過剰に働いて膝が痛む」場合だ。確かに「膝がバランスをとるために働く」部分は問題解決になっているのだが、それが「過剰に働く」によって「膝の痛み」という新たな問題を生み出している。
CAMRでは、このような「新たな問題を生み出す」問題解決のことを「偽(にせ)解決」と呼ぶ。偽解決はもともと家族療法などの心理療法で使われる言葉で、私たちの身の回りにも溢れている現象である。
たとえば圧迫骨折のおじいちゃんは「痛うて動けん。痛いのが治ったら動くわい」という問題解決を図って痛みが消えるまで寝て過ごそうとするが、いつのまにか廃用という問題が生じて動けなくなってしまう。
学校でイジメの問題が起きると、先生がみんなに厳重に注意する、あるいはみんなを叱る。そうすると「イジメの潜在化」という新しい問題を生み出す。
政治家は「内容についてはこれから様々の議論を尽くす」とその場しのぎに答えるが(特定の政治家のことではありません(^^;))、結局解決を先送りにし、手遅れになってより困難な問題を生み出す。
つまり一見問題解決には見えるのだが、新たな問題を生み出して、より問題を複雑、あるいは悪化させ、解決をより困難にするようなものが「偽解決」と呼ばれるわけだ。
人の運動システムが自律的に行う問題解決にももちろん「偽解決」が混じっている。というのも運動システムの自律的問題解決は、筋力などの運動リソースが失われた中で、あり合わせのものを使って何とか問題解決を試みている。必ずしも上手く行かないことも多いのである。
そうするとセラピストの重要な役割の一つは、患者さんの運動システムが自律的に生み出した問題解決スキルが、適切な問題解決の状態を生み出しているかあるいは偽解決なのかをまず見分けることである。そしてそれが解決可能なものかを見分けることが重要である。
通常は運動問題が生じたその後で、行為者の運動システムが自律的に選択した解決策なので修正可能なことも多い。そうすると上手く偽解決の状態を、問題解決の状態に近づけることができるわけだ。 詳しくは次回に。(その5に続く)
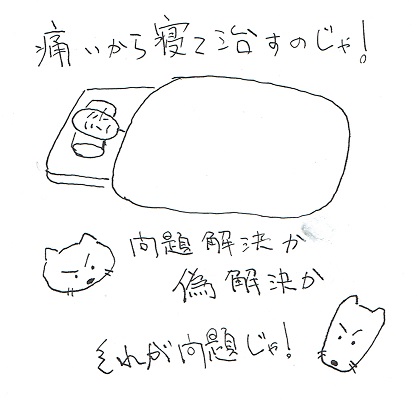
【CAMRの最新刊】
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」
【CAMRの基本テキスト】
西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版
【あるある!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」
【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①
【CAMR入門シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①
西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②
西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③
西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④
西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!



「代償運動」って本当に悪い?(その3)
セラピストが「代償運動」という言葉を問題として指摘するとき・・・・セラピストがその問題を解決できる時はなんの問題もない。しかし問題解決できない時には、問題だけを指摘するだけである。つまり「代償運動」は患者さんを苦しめるは「悪魔のささやき」となるかもしれない。
たとえば片麻痺患者さんは苦労して分回し歩行というスキルによって漸く歩けるようになったのに、「その歩き方は良くない。間違っている」などとセラピストから指摘される。そしてセラピストの治療なるものに従うもののいつまで経っても麻痺は治らず、分回し自体が消えることはないからだ。
患者さんは頑張っても健常者の様に歩けないので、努力が足りないと自分を責めたりする。反省的なセラピストは自分の力が足りないと自分を責めたりもする。そうでもないセラピストは「患者の努力が足りない」とか「私の言うことを聞かないからだ」と患者さんやその家族を責めたりする・・・・やれやれ、随分こんな場面を見てきた。
この問題を解決するには、まず悪い運動を意味する「代償運動」という言葉を使わないことだ。代わりにCAMRでは、障害などの後に現れる運動の多くは、「自律的問題解決の運動スキル」と呼んでいる。これは長いので普通、「問題解決スキル」と略す。
なぜなら人の運動システムでは、麻痺や痛みなどの運動問題によって必要な生活課題が達成できなくなると、自律的・自動的に何とか問題を解決して必要な課題を達成しようとする本質的な性質が備わっているからだ。
つまり前々回見たような「足関節が硬い」場合は自律的に「膝でバランスをとる問題解決スキル」を生み出す。また「片麻痺がある」場合は、「分回しという問題解決スキル」を生み出して、歩くという課題を達成している。
麻痺や可動域低下などの運動問題を自律的に解決して、課題を達成するための運動スキルであるので、本来的に悪い運動ではない。これは人の運動システムが自然に備えている課題達成のための能力なのである。
たとえば右膝を打撲して荷重すると痛い。そうすると右脚に荷重しないで移動する様々な問題解決スキルが生まれる。左脚のケンケンや右脚への荷重時間が短い跛行などのスキルも見られる。また左脚はすり足で振り出して右脚の負担を小さくして痛みを軽くするかもしれない。あるいは右下肢荷重時には両手で家具や手すりを持って痛みを生じないように移動するかもしれない。いずれも右膝の痛みを軽くして移動するための問題解決スキルである。
上記の場合、いずれの問題解決スキルも荷重に右脚をできるだけ「使わない」ようにする意図があるので、CAMRでは「不使用の問題解決」と分類される。 腰痛ヘルニアで激痛がある場合、体を硬く棒のようにして痛みを小さくするように歩かれる。これは体全体を硬くするため「外骨格系問題解決」と分類される。 このようにCAMRでは全部で6個の問題解決スキルが分類されている(詳しくは「リハビリのシステム論-生活課題達成力の改善(前・後編)」西尾幸敏を参考にしてください)
つまりこれまで「代償運動」と呼ばれていた運動は、「問題解決スキル」と呼んだらどうか。本来的に問題解決をしようとしているので「分回し歩行」は悪い運動ではない。努力の結晶である。患者さんもセラピストもそう評価したらどうか。
ただし、問題解決スキルは全てが良い結果になるわけではない。それらの問題解決は、応急的なその場しのぎであって、そのために新たな問題を生み出すこともある。その新たな問題を生み出すような問題解決スキルは「偽(にせ)解決」と呼ばれる。 次回はこの「偽解決」について検討しよう!(その4に続く)
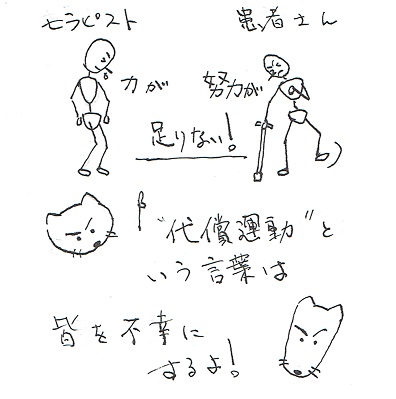
【CAMRの最新刊】
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」
【CAMRの基本テキスト】
西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版
【あるある!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」
【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①
【CAMR入門シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①
西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②
西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③
西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④
西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!



「代償運動」って本当に悪い?(その2)
今回のシリーズでは普段臨床で何気なく使っている「代償運動」について様々な角度から検討している。
前回は「代償運動」の定義や「歩行時の膝痛の原因の一つが、足関節の硬さのために大地の起伏を十分に吸収できないために膝関節に過剰な代償運動が起きること」というアイデアを紹介した。
前回は「代償運動」という言葉を使うことで、因果の関係も上手く説明できて「やはり修正するべき運動」と考えられる。
「何だ、それで良いではないか」と言われそうだが、どうもことはそんなに単純ではない。問題は「代償運動」=「好ましくない運動であり、修正するべきである」という単純な思い込みである。
たとえば脳卒中後の分回しの原因は、脳の細胞が壊れたことで麻痺が起こり、患側下肢を振り出せなくなることである。仕方なく健側下肢や体幹を使って健側へ大きく重心移動して患側下肢を浮かせ、更に体幹を振り回すことによって患側下肢を振り出して歩行をする訳だ。
セラピストの多くは、分回し歩行は「本来の歩行方法ではなく代わりの歩行方法、つまり代償運動である」と思うのかもしれない。
実際に僕の周りにも「分回し歩行は代償運動なので治したい」というセラピストが少なからずいた。なぜなら「本来の運動とは『健常者の歩行方法』であり、それから大きくずれているから」などと言う。
しかし麻痺のある体でも、麻痺のない健常者の歩行の形が「本来の歩行方法」なのだろうか?それはやはりおかしい。半身に麻痺がある体では、分回し歩行こそ、本来の歩き方ではないのか?
脳性運動障害では運動障害の原因は麻痺である。麻痺を治すことができるなら問題ないが、我が国でもこの「麻痺を治す」というアプローチが導入されて半世紀以上が経つが、未だに「麻痺が治る」と証明する科学的報告はなされていない。これは実現不可能な目標なのだろう。
つまり「麻痺があっても効率的で美しい健常者の歩き方を目指すべきである」という健常者への同化主義(努力して健常者に近づくべき、など)が背景にあるのかもしれない。
このような同化主義に支配されていると、「それは人本来の効率的な歩き方ではない。健常者の歩き方が本来の歩き方だ」と問題は指摘する。が、その問題の原因である麻痺を解決する方法はない。麻痺は治せないからだ。つまり解決手段もないのに「代償運動」だと問題だけを指摘するのはいかがなものか。
「代償運動」という言葉は、「本来の運動ができないので代わりの運動」という意味がある。そうすると「本来の運動」をどう捉えるかで、「代償運動」の意味が変わってくる。本来の運動を健常者の歩行の形に求めたのでは、麻痺のある人はどうしようもないではないか。
前回の膝痛の例では足関節の可動域を改善できたので「代償運動」というアイデアは上手く機能した。しかし、もし足関節が強直などで可動域を改善できなかった場合はどうなるのだろう?やはり代償運動と問題は指摘しても解決はできないのではないか。
代償運動と問題を指摘して、その原因が上手く解決できる場合は良いものの、上手く解決できない場合にも、「代償運動だ!」と問題を指摘するが、解決できないので患者さんは苦しめられているのではないのか? 患者さんは麻痺のある体で何とか苦労して「分回し」というスキルを発見し、麻痺肢の振り出しの問題を解決して歩けるようになった。しかしセラピストから「それは代償運動だから良くない」と批判されたのではたまったものではない。
これが「代償運動」という言葉の問題である。治せる場合も治せない場合もひっくるめて「代償運動」と一括りにして悪者扱いしてしまうわけだ。 ではどうするか?(その3に続く)
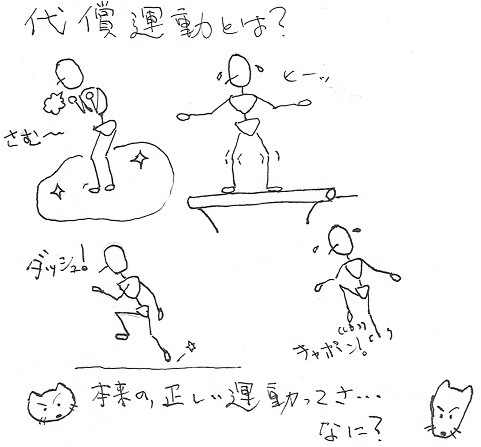
【CAMRの最新刊】
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」
【CAMRの基本テキスト】
西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版
【あるある!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」
【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①
【CAMR入門シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①
西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②
西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③
西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④
西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!



「代償運動」って本当に悪い?(その1)
「代償運動」の「代償」の意味は、広辞苑によると「(比喩的に)ある目標を達成するために払う犠牲や損害」とか「本人に代わって弁償代弁すること」とか「直接実現できない目標を他の類似したものにおきかえて欲求を充足させること」などがある。そうなると「代償運動」で意味されるのはおおよそ「(犠牲や損害を伴う)問題のある運動」だったり、「本来の運動ができないので代わりの運動」といった意味になるのだろう。つまり「あまりよろしくない運動」というイメージである。
実際、学校を卒業したばかりの新人さんなどに聞くと、やはり「代償運動は悪いことなのでやめさせた方が良い」などと答える。
いや、新人さんばかりでなくベテランセラピストの中にも「代償運動は今は良くても、特定の部位に過剰な運動を強いることでやがて歪みを大きくし、変形・痛みなどの原因になるから、なんとしても修正するべきである」とか「本来の正しい運動をできるように修正するべき」などという方もおられる。
「そうか、そんな風に考えると代償運動は悪いものに違いない」と思う。
たとえば歩行時に膝に痛みを訴える方がいる。最近屋外歩行を始めたら、膝が痛くなったと言われる。近医を受診したら「変形性膝関節症」の診断名がついた。若いセラピストは困ってしまう。「膝が変形したのだから仕方がないとは思うが、何とか膝をよくできないものか?」といった相談を受けることも多い。
こんな時はあまり詳しい説明はしないで、「まず足部の小さな関節のモビライゼーションと足関節のストレッチを十分にしてみて。それでダメなら言って」などと伝える。
そうすると最初のアプローチで「膝の痛みが軽くなった、良くなった」と経験することも多い。「全身の各部位は影響し合う」ということを実際に経験するには良い機会だと思っているのでそうしている。
すると若いセラピストが「あれで膝が良くなったんですね」などと言う。まあ、単純・素朴にそんなことを言う。
こんな時に「代償運動」という言葉は便利かも知れない。以下の通り。
「いや、厳密に言うと膝を治したわけじゃない。あくまでも膝痛の原因の一つとして考えて欲しいが、この方の全身の動きを見ると硬くて各関節の動きは小さくてやや小刻みな歩き方をされる。こんな方は特に足関節や足部の柔軟性などが低下していて、大地の凹凸を上手く足部で吸収できていないことが多い。それでは歩行が不安定になるよね。
そして最近になって屋外歩行を始められた。それで大地からの起伏を吸収して体幹を安定させるために足関節の代わりに膝関節が頑張って過剰に働いて負担がかかっている可能性がある。つまり足関節がうまく機能していないから、膝関節での『代償運動』で揺れを吸収している。
そこでまずは足関節と足部の柔軟性を改善してみる。すると足部が大地のデコボコに上手く適応するようになるので、膝の『代償運動』が過剰に使われなくなり、痛みが軽くなった可能性がある。これがダメならまた次のポイントへアプローチする」
などと説明する。こうするとやはり代償運動は悪い運動で修正するべきとなって、わかりやすいのかも知れない・・・・・いや、たまたまこれが良い例であるに過ぎない。
臨床ではこのように説明に便利な場面が希にあるという理由だけで、この「代償運動」=「好ましくない運動」という図式が当たり前になっているのではないか。この単純な図式によって、実は様々な弊害が生まれているのではないか。どういうことか?
次回からこの「代償運動」という言葉を色々な角度から検討してみたいと思うのだ。(その2に続く)
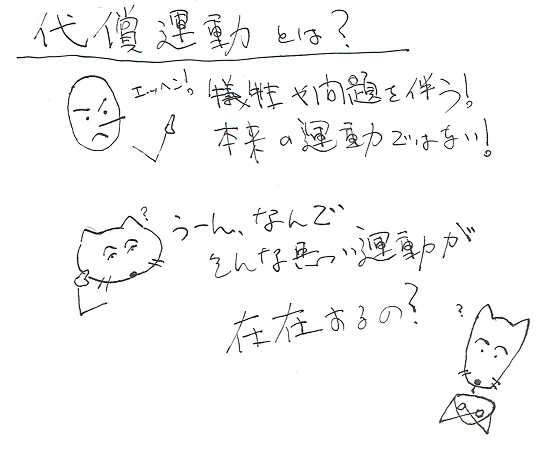
【CAMRの最新刊】
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」
西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」
【CAMRの基本テキスト】
西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版
【あるある!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」
【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①
【CAMR入門シリーズの電子書籍】
西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①
西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②
西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③
西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④
西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!