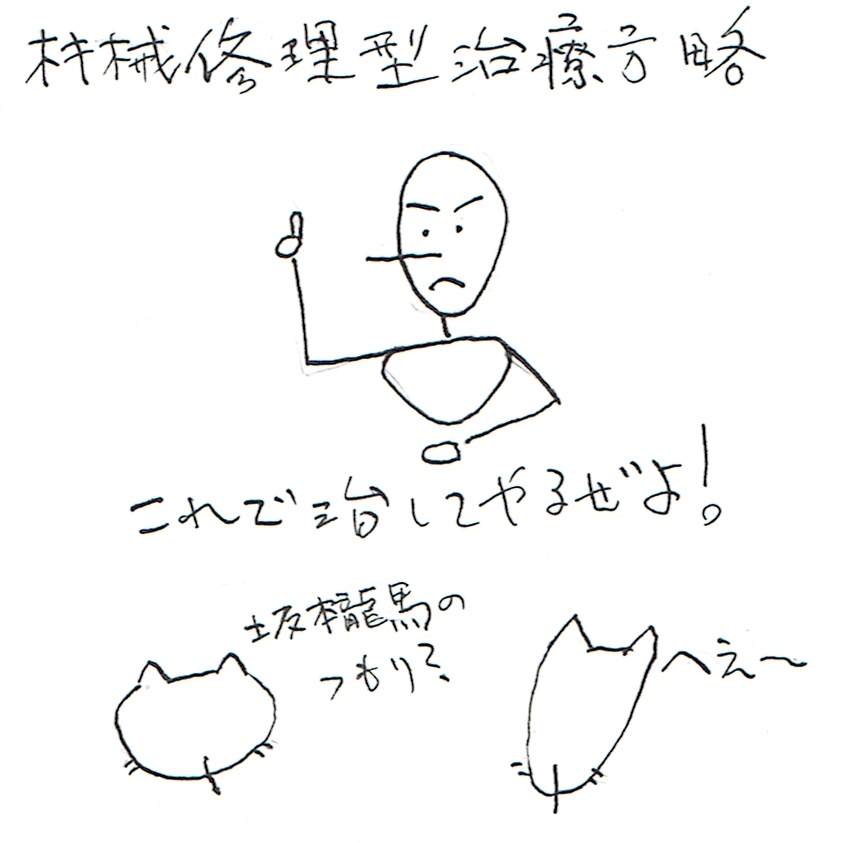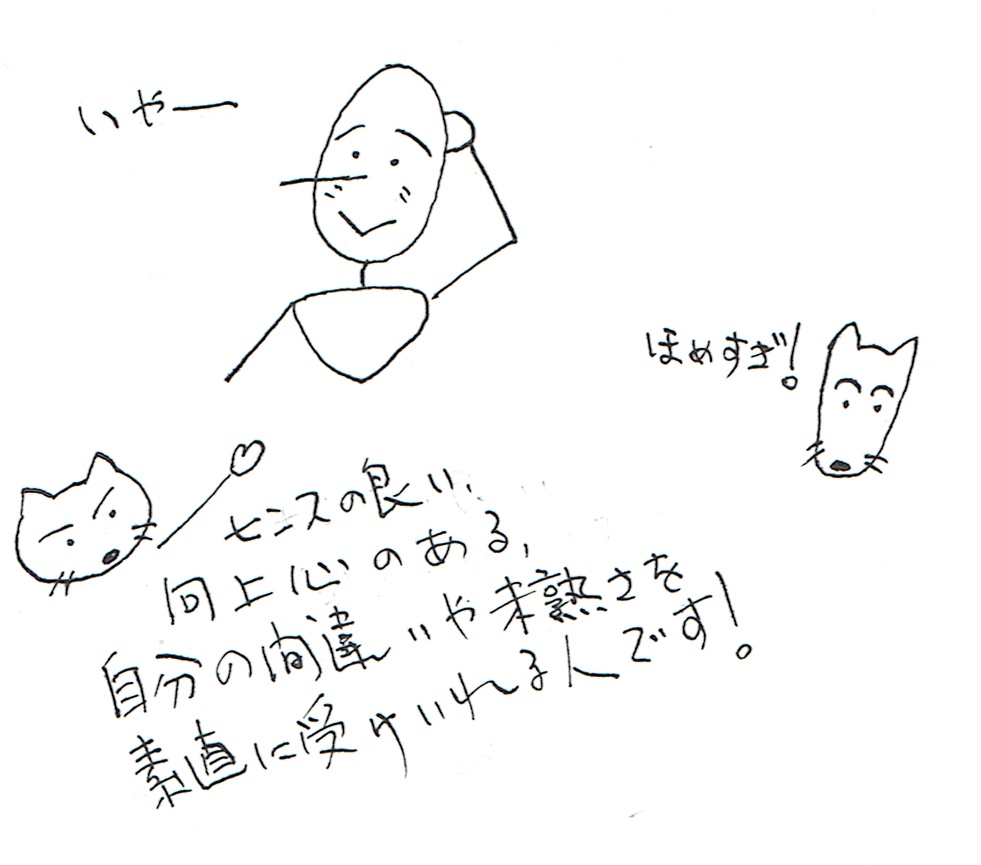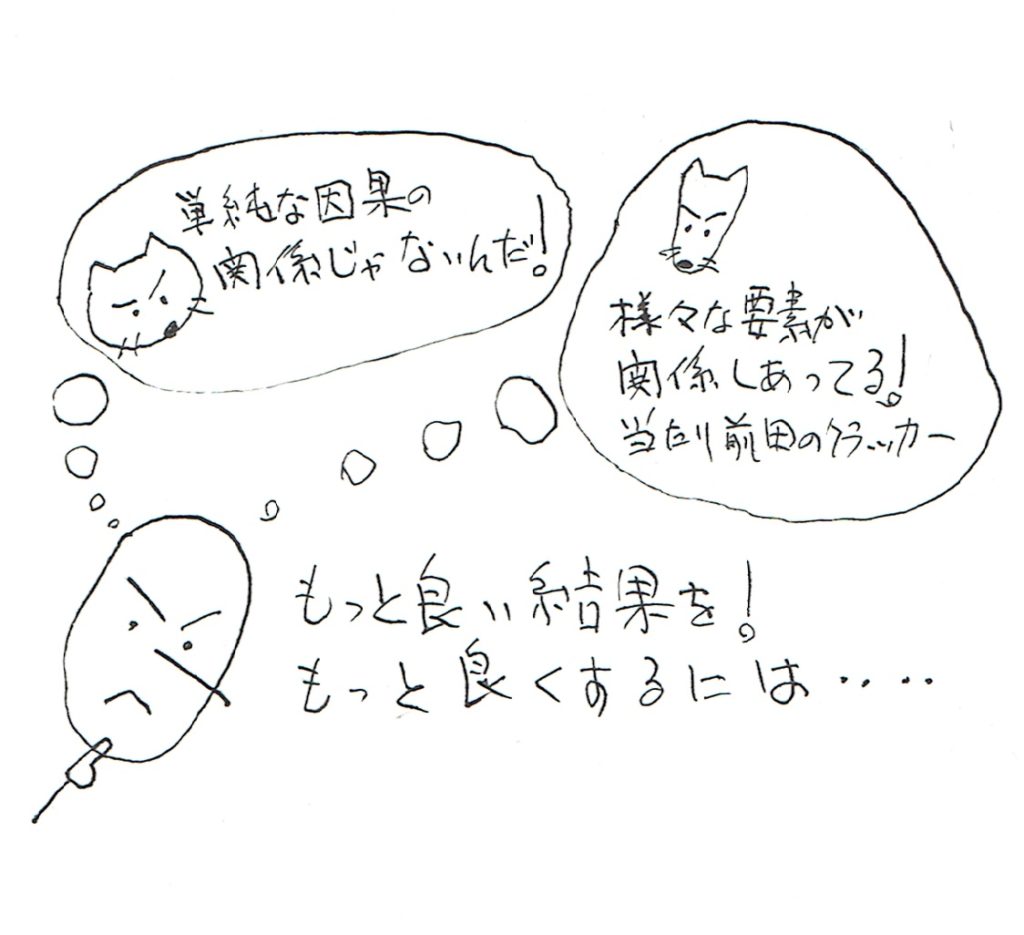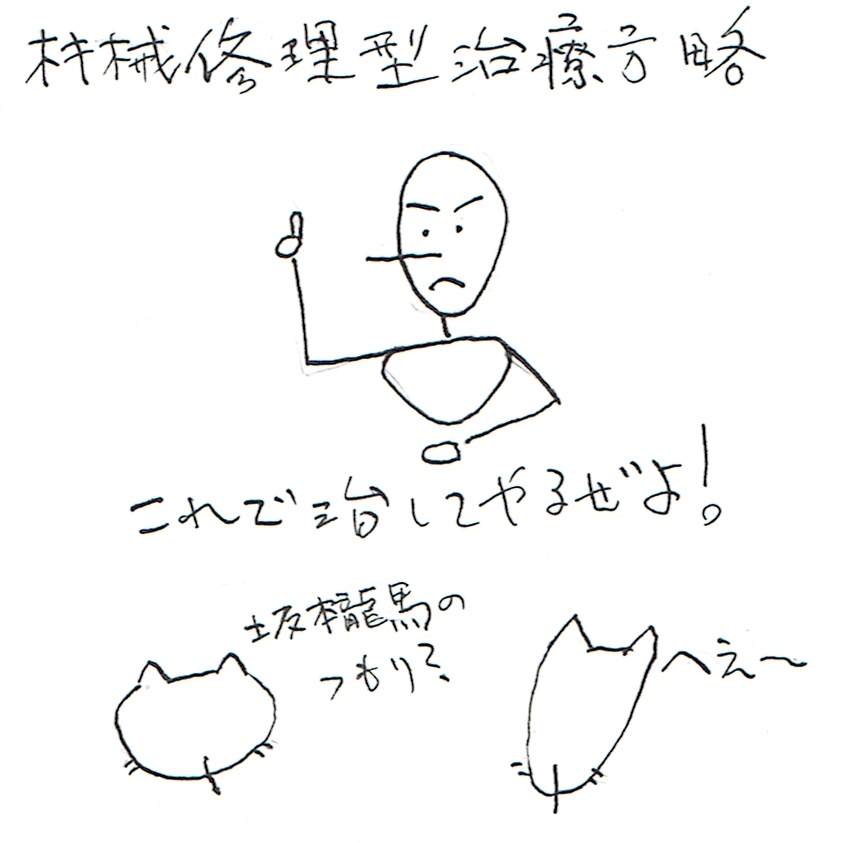臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!
CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!
人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!
詳細はこちら
CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!
講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!
詳細はこちら
CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!
基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!
詳細はこちら
治療方略について考える(その7)
治療方略:治療の目標設定とその目標達成のための計画と方策
さて龍馬君のようなストーリーはセンスの良い、向上心のある、自分の間違いや未熟さを素直に受け入れるセラピストなら、程度の差こそあれ経験しているのではないでしょうか?
最初龍馬君は学校で習ったように、身体の構成要素を基に因果の関係を想定していました。しかしそれでは上手くいかないのです。つまり腰部周辺の軟部組織だけが原因だとする「機械修理型治療方略」だけでは一時的な変化しか起こせないと気づきます。
実際の慢性痛にはより沢山の身体部位が関係し合っている、つまり身体内の軟部組織が幅広く影響しあっていることに気づきます。さらに軟部組織のみではなく、身体内の様々な要素、つまり関節内運動や血液循環の低下、神経の圧迫などと関係する要素群に気づきが広がっていきます。これが素朴なシステム論の第一段階です。つまり身体内の様々な部位・要素の相互作用として腰痛という問題が生じると気がつくのです。
また次にはこの慢性の痛みが、身体の構成要素だけに止まらず、仕事や環境、生活習慣などの相互作用によって生まれていることに気がつきます。痛みはまさに身体だけで作られるのではない。こうなると素朴なシステム論の第二段階です。アプローチする構成要素は身体内に止まらず、仕事環境や運動習慣、生活習慣などに広がっていきます。
つまり運動システムの作動は機械のように明確で単純ではなく、各部位や要素がお互いに影響を受け合って変化しながら1つの状況、つまり腰痛という状況に落ち着いていくことに気がついたのです。龍馬君は経験を通して、運動システムの作動の性質の一つ、「身体のみならず環境や習慣などの各要素間の相互作用によって問題が繰り返し生まれる状況が作られる」ことに気がついたのです。(その8に続く)
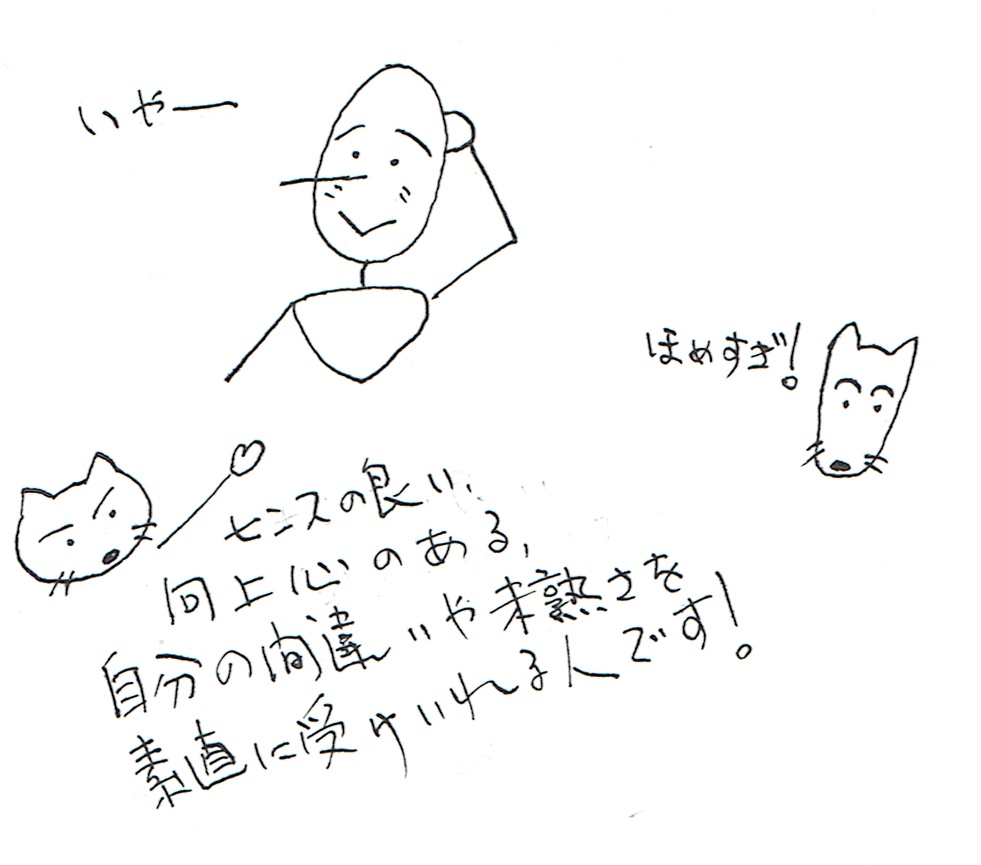



≧(´▽`)≦
みなさん、ハローです!
「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。
今回は「CAMRの旅お休み処 シーズン3 その4」です。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆
CAMRの旅お休み処 シーズン3 その4
「発想を転換してポジティブシンキング、ではないのだ」
秋山です。これまでになくハイペースなお休み処です。
ホームページの「CAMRの基礎にあるもの」で家族療法(短期療法)の話が展開中です。
https://rehacamr.sakura.ne.jp/
その2「問題解決に原因の探求は必要か?」の中で、「前向き志向とは違う」とあります。「発想の転換」は何を変えるのか、に関して。
ちょっと前に「ポジティブシンキング」というのが流行りました。物事を肯定的な方向に傾斜してみる、極端に言えば「良かった探し」です。あの人が私をいじめるのは、ちゃんと育てようと鍛えてくれている、というような。ポジティブシンキング自体は悪いものではなく、困難をやり過ごすのに時に有効です。行き過ぎると現実逃避になるのですが。
家族療法の流れを受けたCAMRで言いたいことは、障害のマイナス面にとらわれて嘆くのではなくプラスの面を見ましょうというのではないのです。「片麻痺になって良かった」と当事者の方が言われることがあります。これはその方が苦労の果てにたどり着いた境地であり、周りから決して言うものではないです。そこを目指しているのでもありません。
では、何か?むしろ、良い悪いの価値には関わらない。悪いを良いに転換するのではなく、障害はおいといて、別のものを見ませんか、という転換です。
まぁ、ポジティブシンキングではないが、楽観的ではあるかも。あ、これはCAMRが、ではなく私だけかも?
★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!



治療方略について考える(その6)
治療方略:治療の目標設定とその目標達成のための計画と方策
こうして龍馬君は痛みの周辺の徒手療法に加えて、より広範囲の柔軟体操やストレッチ、そして腰椎のモビライゼーションなども治療に加えます。もちろんそれによって治療効果は明らかに良くなります。二郎さんが来院してくるのは週1回から2週に1回に減ったからです。痛みが発生するまでの期間が長くなっています。しかし・・・それでも二郎さんは2週に一度は腰痛の治療に通ってこられます。
龍馬君はより良い治療効果を求める向上心と、自分の問題点を受け入れる素直さを持っています。だからこそ、もっと良い効果が得られるように考え、努力します。そうして次のような結論に至ります。「2週に一度という周期で痛みが強くなってくるのは、きっと生活を送る中で周辺の軟部組織がその位の周期で硬くなるような状況にあるからだ。たとえば二郎さんは仕事で長時間同じ姿勢をとっている。そして運動習慣がなく、体を様々に動かしたり、多様な筋活動をすることがないのだ。だからその同じような状況で過ごすうちにいつも同じ身体の軟部組織に硬さが生じてしまうに違いない。だからこの人が置かれている状況自体を変えねばならないのだ!」
こうして龍馬君は次の段階に進みます。広範囲で多様な徒手療法に加え、各種の自己ストレッチや運動を含むホームワークを追加します。こうして二郎さんの通院の間隔は更に1ヶ月に1回と伸びます。
でも龍馬君はまだ満足できません。来院時に二郎さんに聞いてみます。「ホームワークはやっていますか?」「いやあ、できるだけやっているのですが、忙しくなるとついついやめてしまいます」
「なるほど!」と龍馬君はハタと気がつきます。そこで次のように二郎さんに言います。「実はですね、二郎さんの腰痛の原因は、長時間同じ姿勢でいること、あまり体を動かさないことが原因なのです。だから体が自然に同じ姿勢で固まって痛みの原因になるのです。運動しないので筋肉は細くなり、縮み、癒着してしまうのです。その結果、血流が悪くなり、関節の動きを悪くし、神経を圧迫したりもするのです。そしてどんどん腰椎を含む全身が悪くなっているのです。
実は僕にはもうこれ以上できることはありません。だからもし二郎さんが本気で腰痛を治したい、これからの人生を健康に過ごしたいのなら、二郎さん自身がやることを決めて実行していかなくてはなりません」
そうしてこれまでのホームワークに加え、仕事場での姿勢を変えたり、運動をする工夫や日常生活での運動習慣の取り入れ、椅子や照明などの環境設定の工夫等を二郎さんと話し合います。二郎さんも納得して、生活習慣全体の見直しを図ることに熱意を示されました。
こうしてついに二郎さんは来なくなりました。そんなある日、町で二郎さんと偶然出会います。「腰痛はどうですか?」と尋ねると「先生に言われたように歩行距離を伸ばしたり、階段を使ったり、仕事の合間にラジオ体操とストレッチをするようになって腰もすっかり良くなりました・・・あ、それに聞いてください!ある日股関節が痛くなったんですが、思いついて大股で歩くようにしたんです。そしたらそれまで痛かった股関節が楽になることを発見しました。運動って本当に大事ですね!」と明るく笑いましたとさ!めでたし、めでたし・・・・(その7に続く)
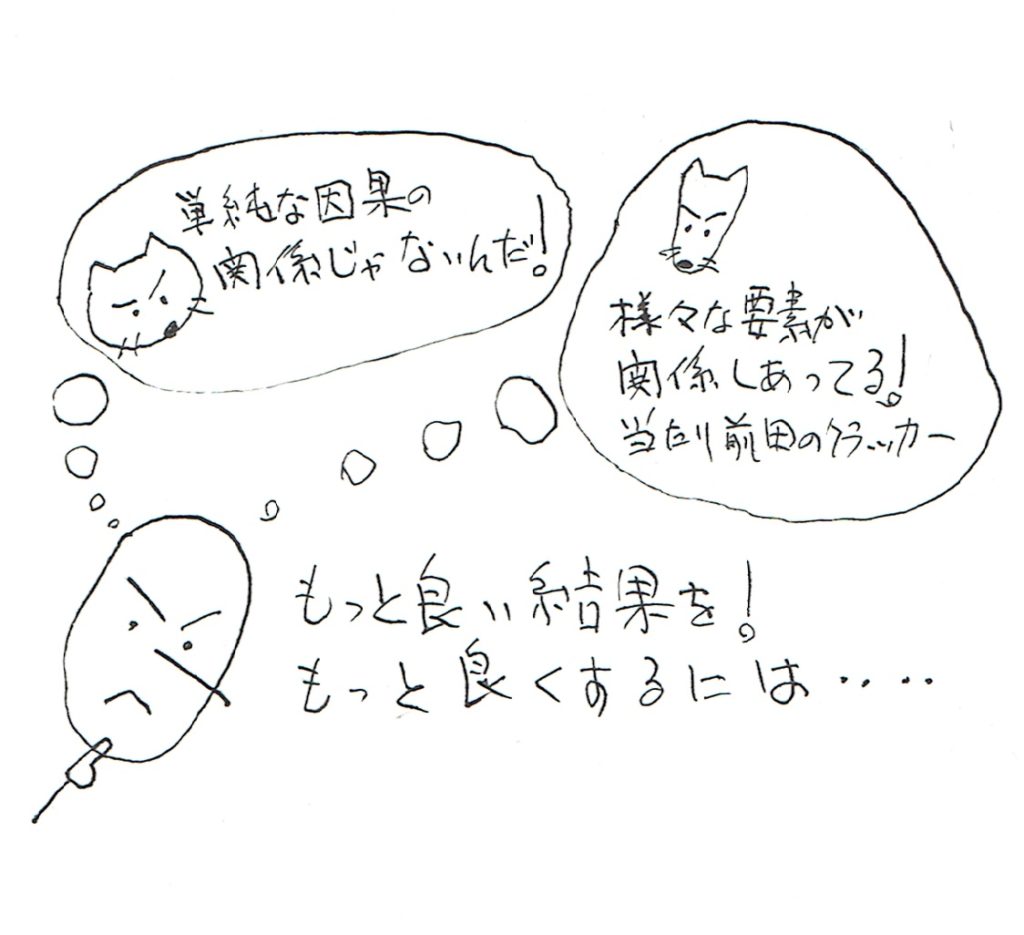



≧(´▽`)≦
みなさん、ハローです!
「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。
今回は「CAMRの旅お休み処 シーズン3 その3」です。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆
CAMRの旅お休み処 シーズン3 その3
「軌跡が決まるのは奇跡的?なんちゃって (^^;) ベルンシュタイン問題続きの続き」
秋山です。タイトルにこりすぎると、ろくなことはないのですが・・・。
その昔、私は養成校の教官をしていまして。その頃の悩みの種が「作業分析」の講義ノート作りでした。当時の教科書には、作業の一般的な分析をやれ、と載っていまして、社会的な意味や精神面への影響などとともに運動についても話さなければなりませんでした。
この作業を遂行するときにどんな動きが必要で、その動きのためにはどこの関節がどの方向にどれくらい動いて、その筋肉は・・・とやるのですが、考えれば考えるほどロボットみたいな動きになるし、使う筋肉も姿勢も入れれば結局全身か?ということになってしまいます。
学生さんに、「この工程の動きの関節可動範囲はこれでいいのですか」と質問されても、「うーん、良いと言えば良いような、それだけじゃないといえばないような」と何とも曖昧な返事で。(当時の皆さん、すみません) 机の上のコップを持つ、という時、人によって動きは違うし、肝心なのはコップまで手が届くことなのに、肩関節がどうとか肘が・・・というのは本筋ではないと思いながらも、共通の一つの答えを探しているようなものでした。
長々と思い出話をしてしまいました。
コップに手を伸ばした時、一度として同じ軌跡を通りません。一回ごとに通り道や速度は異なります。環境が同じでも同じ軌跡を通らないし、ましてや環境が異なればそれに応じた軌跡を通るでしょう。当たり前といえば当たり前ですが、正しいやり方を求めていると見落としてしまいます。
軌跡は異なるのですが、同じ結果を生み出すことができます。手がどう通っていってもコップをちゃんと持てる。この辺のことは、CAMRホームページ 人の運動変化の特徴 その2 異なった方法でいつも同じ結果を出すこと をご覧ください。
ふー、やっと先に進めるかな。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆
p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!



治療方略について考える(その5)
治療方略:治療の目標設定とその目標達成のための計画と方策
さて、前回までで要素還元論の見方から「機械修理型」の治療方略が生まれたこと。その治療方略は一見して人と機械の似た構造を基に治療しようとしていること。しかし実際には機械と人の運動システムではまったく違った構造があり、それによって作動の性質もまったく異なっていることを説明してきました。
要素還元論が見た目のシステムの構造と機能を基に、問題のある要素に焦点を当てることに対して、システム論という視点は構造ではなくシステムの作動の性質に焦点を当てます。そうすると人の運動システムの作動の性質を基に、学校で習ったものとはまるっきり異なった治療方略が生まれてきます。
もっともシステム論と言っても、実は視点や対象、領域によって非常に沢山のものがあります。前シリーズ「システム論について話しましょう!」でも西尾の分類を基に、3種類のシステム論を紹介しました。
今回はその中から、「素朴なシステム論」の視点から見た運動システムの作動の性質を基にした治療原理と治療方略を紹介してみたいと思います。
「素朴なシステム論」とは臨床のセラピストが自然に行き着くシステム論の視点です。具体的には以下のエピソードを通して学んで行きましょう。
ある若いセラピストがいます。名前はとりあえず龍馬君としましょう。彼は学校で習った「機械修理型」の治療方略を引っ提げて臨床へ出ます。そしてしばらく患者さんの運動問題の解決に取り組みます。整形疾患などではこの治療方略で上手く解決する場合もあります。でも全体としては上手くいったり、行かなかったりを繰り返します。
そんなある日、二郎さんという腰痛の方と出会います。龍馬君は徒手療法の講習会で習ったように姿勢を見て、脊柱の可動域や周辺の軟部組織を触診し、筋力を評価し、結果痛み周辺の軟部組織が硬くなっていることを見つけます。そして適応のある徒手療法を実施します。二郎さんは「痛みが軽くなった。良くなるなんて初めてだ。先生、すごい!」と喜ばれます。そして龍馬君は「また痛くなったら来てください」と送り出します。表情には出しませんが、実は龍馬君も鼻高々です!「やはり学校で習った機械修理型の治療方略が上手く機能したな!」
ところが一週間後に二郎さんが、「腰がまた痛くなった!」と来られます。見ると前回と同じ様子で、また同じ徒手療法で治し、送り出します。しかしまた一週間後には・・・ このような経験を繰り返すうちに、龍馬君は次第に「痛み周辺の軟部組織の硬さ→痛み」というこの単純すぎる因果関係に疑問を持つようになります。龍馬君は次のように思います。「考えてみると筋膜で全身はつながっている。この方は姿勢も良くないし、腰以外の他の身体部位にも悪いところがあるに違いない。いろいろな要素が影響してるんだ。だからもっと広範囲に悪いところを探した方が良いな!」(その6へ続く)